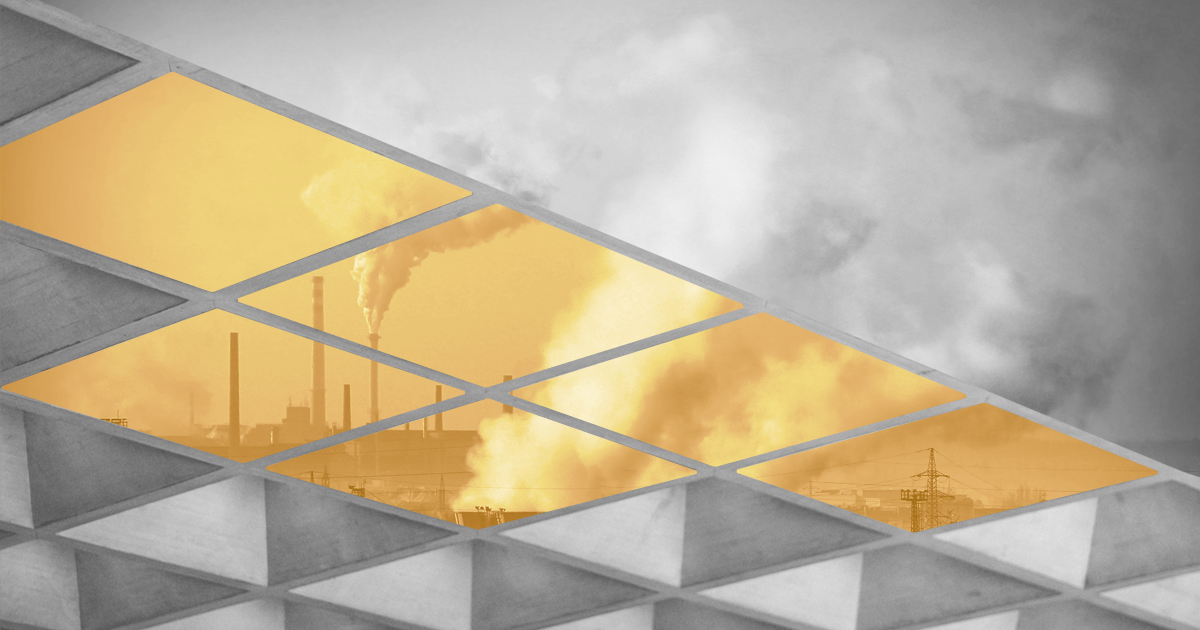- 「投融資先の排出量」とは、投資家や金融機関が手がける金融サービスや投融資に由来する温室効果ガス排出量のことです。
- 「投融資先の排出量」の報告は簡単ではありません。データ収集、データ収集の標準化、規制準拠など、多くの課題があります。
- 現状、「投融資先の排出量」の算定・報告はほとんど任意です。一方で、”GFANZ”のようなアライアンスや、”Race to Zero”、”PCAF”のようなイニシアティブは、この分野の進展に尽力しています。
- 金融機関は、GHGプロトコル、PCAF、SBTiなどの組織・ガイドラインが提供する基準、フレームワークをベースに、パーセフォニのようなプラットフォームを活用することで、「投融資先の排出量」を算定・報告し、削減努力に繋げることができます。これらのリソースを用いることで、金融機関や企業は、説明責任を全うし、低炭素経済への移行に貢献することができます。
低炭素経済への移行に必要な資金を供給するうえで、金融機関は大きな責任を負っています。なぜなら、金融機関は、気候変動による最悪の影響を和らげる力を持っているからです。気候変動の緩和策や適応策に投資するだけでなく、資産の割り当てを調整したり、ポートフォリオを脱炭素化することも可能なのです。
In addition to managing greenhouse gas (GHG) emissions created from their day-to-day activities, financial institutions are also accountable for financed emissions. These are the emissions related to loans, underwriting, investments, and other financial services.
CDP(環境情報開示システムの国際的運営団体)の報告書「グリーンファイナンスの時代」によれば、「投融資先の排出量」は金融機関による直接の温室効果ガス排出量の約700倍に上ります。最近リリースされた別の報告書によれば、気候変動に関するパリ協定が採択されてからの6年間、つまり2015〜21年に、化石燃料企業(事業)に銀行が投資した資金は、世界上位60行の合計で4兆6,000億ドルにも達するとのことです。2021年だけを見ても、その額は7,420億ドルに上ります。
このような状況の中、温室効果ガスの排出・吸収量を差し引きゼロにする「ネットゼロ」を公約している金融機関は、ただちに「投融資先の排出量」の管理に取り組む必要があります。本記事では、投融資先の排出量とは何か? なぜ重要なのか? など、その測定と管理をめぐって金融機関が把握すべき事柄の基本をわかりやすく解説します。
「投融資先の排出量」とは?
「投融資先の排出量」とは、投資家や金融機関が手がける金融サービスや投融資に由来する温室効果ガス排出量のことです。炭素会計の国際基準である「GHGプロトコル」では、スコープ3(バリューチェーンから生じる間接的な排出)のカテゴリ15(投資)に分類されています。
パリ協定の目的の一つに「資金の流れを、温室効果ガス排出削減と気候レジリエンスの実現に向けた道筋に適合させる」ことがあります。しかし、金融機関や投資家は現在、化石燃料産業など排出量の多い産業に巨額の資金を投資しています。そのため、パリ協定の目的を果たす上で、金融機関や投資家が担う役割が大きいと言えるのです。
なぜ「投融資先の排出量」が今世界で注目されているのか?
「投融資先の排出量」が重要なのは、世界の温室効果ガス総排出量の中で相当な割合を占めているからです。
自然保護団体「シエラクラブ」の最近の報告によると、米国金融業界単体だけで、一つの国が排出するレベルの温室効果ガスを排出しています。米国金融業界を一つの国とみなした場合、その総排出量は世界の国の中で第5位となり、4位ロシアとの差はわずかです。その事実を裏付ける数字としては、米国最大手の銀行8社と資産運用会社10社は、2020年、合わせて19億7,000万トンCO2e(二酸化炭素換算値)排出量相当の資金源となっているのです。
しかし「投融資先の排出量」を測定している金融機関の割合は25%にすぎません。また、その中でも、49%の金融機関はポートフォリオの排出量を的確に管理・分析できていません(CDP「グリーンファイナンスの時代」の報告)。
現在、世界の温室効果ガス排出量の帳簿には大きな穴が開いた状態です(未報告が非常に多い)。厳しい言い方をすれば、「投融資先の排出量」を生み出している金融機関は、自らが増やした排出量への説明責任をうまく逃れている状態、とも言えるでしょう。
「投融資先の排出量」を算出・管理しないリスクは、世界の気候だけでなく、金融機関や投資家の社会的評価と資産にも及びます。逆に、「投融資先の排出量」を適切に算出・管理することで、銀行や資産運用会社は商品・サービスが、気候にどのような影響を及ぼしているのかといった”炭素コスト”を把握できるようになります。さらに、低炭素社会への移行をビジネスチャンスに転換することも可能なのです。
「投融資先の排出量」を適切に報告することは難しい?
「投融資先の排出量」の報告に際して、世界的に100%標準化された規格はまだ存在しません(世界の金融機関が準拠する暫定的な基準は存在します)。金融機関としては、専門家のアドバイスがない場合、正しい情報を見極めることが難しい状況が続いています。
環境団体の「世界資源研究所(WRI)」による予備調査報告書「気候公約の先の銀行業——ネットゼロの将来に向けた顧客エンゲージメントと商品・サービスの変革」は、金融機関が「投融資先の排出量」を算出・管理することに関して、以下の課題を取り上げています。
- 必要なデータの評価・収集・生成に多大な時間、資金、資源がかかる。
- 測定において、必要なナレッジが欠けている。
- グリーンボンド(環境債)の追加性と代替可能性(環境債でなければ排出削減事業の資金が調達できないこと)を精査しなければならない。
- 各国政府や金融規制当局による制約があり、パリ協定に沿った意思決定が進まない。
- 的確な算定ツールへのアクセスがなく、算定が曖昧になり、期せずしてグリーンウォッシュ(環境配慮を騙ること)に加わってしまう恐れがある。
「投融資先の排出量」に必要なデータ収集がそもそも困難であったり、算定に利用するデータや算定手法の知見がない。そういった要因が、金融機関のネットゼロ目標推進を阻んでいます。
一つの大きな原因と考えられるのは、ポートフォリオ企業から十分なデータを得られないことです。ポートフォリオ企業の中には、質の高いデータを持っていなかったり、報告するのに十分な排出量データをそもそも収集していない企業が少なくありません。
それだけでなく、世界的な基準に準拠して算出できていない場合、開示データを金融機関どうしで比較できないといった問題も起こり、投資家からの信頼を損なう可能性もあります。

「投融資先の排出量」報告を取り巻く世界の動向
現在、米国を含む多くの国で、「投融資先の排出量」(スコープ3カテゴリー15)の報告は任意とされています。しかし、今後は法規の改正により、報告義務が拡大していくでしょう。たとえば、ニュージーランドは保険会社や銀行、その他の金融機関に対し、気候関連の影響について情報開示を義務付けています。
また、「投融資先の排出量」を報告する協定を金融機関が互いに結び、同盟や共同体のような組織を結成する動きもあります。
レース・トゥ・ゼロ運動
「レース・トゥ・ゼロ(Race To Zero)」は、「国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)」の下で実施されている世界的運動です。あらゆる層から支持を集め、ネットゼロへの取り組みを先導しています。有志の金融機関でつくる「ネットゼロのためのグラスゴー金融同盟(GFANZ)」も、レース・トゥ・ゼロに合わせて目標を定めています。
ネットゼロのためのグラスゴー金融同盟(GFANZ)
ネットゼロを目指す金融機関の世界的同盟は多く、「ネットゼロのためのグラスゴー金融同盟(GFANZ)」は、それらの統合を目指す組織です。すでに450余りの金融機関が加盟し、総資産は130兆ドルを超えています。
以下の同盟やイニシアチブは、すべてGFANZの傘下です(括弧内日本語は仮訳)。
- Net-Zero Banking Alliance (NZBA)ネットゼロ・バンキング・アライアンス(NZBA、ネットゼロ銀行業同盟)
- Net Zero Asset Managers Initiative(NZAMI)ネットゼロ・アセット・マネジャーズ・イニシアチブ(NZAMI、ネットゼロ資産運用会社イニシアチブ)
- Net-Zero Asset Owner Alliance(NZAOA)ネットゼロ・アセット・オーナー・アライアンス(NZAOA、ネットゼロ資産所有者同盟)
- Paris Aligned Investment Initiative(PAII)パリ・アラインド・インベストメント・イニシアチブ(PAII、パリ協定に沿った投資イニシアチブ)
- Net-Zero Insurance Alliance(NZIA)ネットゼロ・インシュアランス・アライアンス(NZIA、ネットゼロ保険同盟)
- Net Zero Financial Service Providers Alliance(NZFSPA)ネットゼロ・フィナンシャル・サービス・プロバイダーズ・アライアンス(NZFSPA、ネットゼロ金融サービス提供者同盟)
- Net Zero Investment Consultants Initiative(NZICI)ネットゼロ・インベストメント・コンサルタンツ・イニシアチブ(NZICI、ネットゼロ投資顧問イニシアチブ)
GFANZは、傘下の同盟やイニシアチブとともにレース・トゥ・ゼロの指針に従って活動しています。加盟している金融機関は、1. 自らのポートフォリオをネットゼロへと移行させること、2. ネットゼロ目標に沿った投資を支援すること、3. 2050年までにネットゼロを実現するという世界目標の達成を後押しすること、を公約しています。
一連の同盟やイニシアチブによる貢献は、それだけではありません。たとえば、「PAII(パリ協定に沿った投資イニシアチブ)」は、資産の所有者や運用会社によるネットゼロ目標の策定を支援する「ネットゼロ投資枠組み」をつくりました。
PCAFとは?「投融資先の排出量」との関係は?
金融向け炭素会計パートナーシップ(PCAF)は、世界の金融機関が連携することによって生まれた枠組みです。「投融資先の排出量」の測定を支援する枠組みを開発・管理しています。
PCAFの枠組みは2015年に開発されました。「投融資先の排出量」の算出において、説明責任や比較可能性が強く求められる世界的なトレンドが誕生の原因です。この枠組みは、GHGプロトコルのスコープ3カテゴリ15を元につくられました。
現在PCAFには、「投融資先の排出量」の測定・開示を公約した300近い金融機関が参加しています。PCAFの大きな目的の一つは、投資や融資に由来する温室効果ガス排出量を合理的に開示できる方法をつくり、運用することです。
この目的を果たす手段として、PCAFの枠組みは算出式を示しています。主要資産クラス6種類について、それぞれの取引に由来する炭素排出量を割り出す算出式です。標準化した算出式が示されたことにより、金融業界全体で「投融資先の排出量」を比較できるようになりました。
PCAFは、CDPの環境情報開示システムや科学的根拠に基づく目標(SBTi)、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)にも準拠し、それぞれが定める報告・補完ガイドラインの合理的な運用を図っています。最終的な目標は、排出削減とパリ協定への準拠で、金融機関が自らのポートフォリオを脱炭素化することです。
「投融資先の排出量」の算出方法
「投融資先の排出量」の算出では、対象の活動で生じる温室効果ガス排出量に着目し、それを金融機関に割り当てます。融資や投資、社債購入のそれぞれに対し、2段階の会計手順があります。
- 融資や投資、金融サービスの対象となった活動の炭素排出総量を推計する
- 共通の算出方法を用い、当該金融機関が責任を持つ分の排出量を割り当てる
明確な報告規格がない場合や十分なデータが手に入らない場合、算出に際して推測や仮定が必要になることもあります。
幸い、多くの機関やイニシアチブにより、会計手順を迅速化させ、規格やデータの不備を補う手段が開発されています。たとえば、「国際エネルギー機関(IEA)シナリオ」は、規格やデータが欠けた状況での分析を支援しています。また、排出量の報告を始める企業や団体が増え、データの質・量が高まるにつれて、仮の数値を使う必要性も薄れていくでしょう。
その他役立つガイダンスも、多くの組織やイニシアチブによって作成されています。たとえば、PCAFが定めた「金融業界向けグローバル温室効果ガス会計・報告基準」(通称「基準(ザ・スタンダード)」)は、「投融資先の排出量」の報告に関するガイダンスを拡充する内容です。現時点では、以下の6種類の資産クラスに関する算出ガイダンスが定められています。
- 上場株式・社債投資
- 商業用不動産
- ビジネスローン(非上場企業等への融資)、非上場株式投資
- 住宅ローン
- 車両ローン
- プロジェクトファイナンス

PCAFは今後、炭素会計状況の進展と入手できるデータ範囲の増加に合わせ、「基準(ザ・スタンダード)」に掲載する資産クラスと事例を適宜追加していく予定です。「基準(ザ・スタンダード)」には、十分なデータが手に入らない場合に備え、データの質を評価するためのガイダンスも掲載されています。
「投融資先の排出量」の測定・削減・開示に役立つツール
現在、金融機関が利用できる、排出量測定の標準的なガイダンス・枠組み・ツールがさまざまな組織によって開発され、提供されています。
「投融資先の排出量」を削減するには、まず測定と開示をしなければなりません。しかし残念ながら、「投融資先の排出量」は測定が難しいことで知られており、そもそも測定業務に乗り出していない金融機関が大半であり、測定・報告していたとしても、内容にしばしば誤りが見られます。
測定が難しい理由は、とにかく大量のデータが関わることです。大手の銀行や証券会社は数百万人の顧客を抱え、多くの金融商品を提供しています。その商品ごとに、「投融資先の排出量」のデータ収集や数値算出が必要になるので、その膨大さは簡単にイメージできるでしょう。
ガイダンスと標準化団体
金融機関による「投融資先の排出量」の報告を後押しする必要性は、多くの団体が認識しています。以下、現在の主な基準や標準化団体を紹介します。
GHGプロトコル
GHGプロトコルは1998年につくられた初の炭素会計基準で、知名度と普及度は現在世界一と言えます。「投融資先の排出量」はGHGプロトコルのスコープ3のカテゴリ15に分類されていますが、このカテゴリのガイダンス粒度はそれほど細かくありません。
PCAF(金融向け炭素会計パートナーシップ)
金融向け炭素会計パートナーシップ(PCAF)は、金融機関にとって素晴らしいリソースです。PCAFは”金融向け炭素会計”の基準を定めるだけでなく、「パリ協定準拠戦略枠組み」も開発しました。このガイダンスは、ポートフォリオ排出量の管理について金融機関向けに開発されたものです。パリ協定への適合性をどうしたら高められるのか?などがわかりやすくまとめられています。次の3つの特徴があります。
- パリ協定のうち、金融機関に関わる領域を説明・強調している
- 頻出用語集がある
- 既存の施策、ツール、プロジェクト、手法の概要を説明している
これから「投融資先の排出量」の管理をスタートさせる金融機関にとって、このガイダンスは素晴らしい手引き書になります。現状を大局的に理解したいとか、自らに最適なパートナーやリソース、さらには将来の展望を見いだしたいという要望に応えてくれる内容です。PCAFはこのような文書を提供しているだけでなく、ワークショップやウェブセミナーなども主催・開催しています。
ネットゼロのためのグラスゴー金融同盟(GFANZ)
2021年4月、ネットゼロのためのグラスゴー金融同盟(GFANZ)が発足すると、世界最大手の金融機関が相次いで加盟しました。GFANZは年次発行の「プログレス・レポート」で、同盟の活動や進捗などを説明しています。発足以降、金融業界の炭素排出削減に向けた公約づくりや、各セクターで取り組める個別ガイダンスの策定を目指し、歩みを進めています。
科学的根拠に基づく目標イニシアチブ(SBTi)
「科学的根拠に基づく目標イニシアチブ(SBTi)」は、金融機関が「科学的根拠に基づく目標(SBT)」を設定する際のガイダンスです。SBTとは、パリ目標(1.5度)を達成するための目標指針です。最新の科学研究の成果がベースとなっています。
算定ツールや指標
財務会計と同じく、炭素会計(GHG排出量算定・可視化・分析)を行う際は、的確なツール(ソフトウェア)を利用して炭素排出量を正確に測定することがとても大切です。炭素会計業務は長い時間と多額の費用がかかり、コンサルティング会社がスプレッドシートの上で行う複雑な作業、というのがこれまでの常識でした。しかし、今はデジタルツールのおかげで数値算出が自動化され、間違いも起こりにくくなっています。
パーセフォニの炭素会計プラットフォーム
パーセフォニの炭素会計プラットフォームは、「投融資先の排出量」の測定にかかる時間と費用を劇的に減らすことを一つの目的に開発され、日々進化しています。
パーセフォニの特徴は、炭素会計の二大基準であるGHGプロトコルとPCAFを同じプラットフォーム内で同時に利用できる点です。自社の排出量(GHGプロトコルを利用)だけでなく、「投融資先の排出量」(PCAFを利用)の算出も同時に行えるため、銀行や資産運用会社にとって、特に使い勝手の良いツールとなっています。
パリ協定資本移行評価(PACTA)
「パリ協定資本移行評価(PACTA)」は、銀行向けの評価指標です。さまざまな気候変動シナリオに対するポートフォリオの適合度を測ることができます。潜在的なリスクやその影響を数値として把握することができます。
「炭素税(カーボンタックス)」と「排出権取引」の違いは?
「炭素税」とは、炭素排出量に応じて企業に課される税のことです。とはいえ、この概念があるからといって排出量を直接制限することには繋がりません。一方、「排出権取引」は、政府が企業に排出量の上限を課した上での、企業間の炭素の取引(システム)を意味します。これらのプログラムは、金融機関のポートフォリオの脱炭素化が遅れれば、最終的に金融機関の負担になります。これらのプログラムは、通常、政府および管轄区域が運営しています。
両者とも、金融機関にとっては(単体の企業と比較して)比較的大きなコストを生み出しかねないシステムとなります。たとえば、カナダ政府は「炭素汚染価格制度」を導入しました。この制度では、1. 運輸部門の化石燃料消費に対する「燃料課徴金」、そして、2. 産業部門での「排出量ベース課徴金システム(OBPS)」という形で、企業の炭素排出に料金を課しています。
排出権取引制度とは?
「排出権取引制度」では、個別の企業や団体に排出量の上限を課し、排出を認める量を「アローワンス(排出枠)」として割り当てます。たとえば、米国環境庁(EPA)の定める「排出権取引制度」では、発電所などに対して排出量上限とアローワンス(排出枠)を設定しています。
「排出権取引制度」は別名「キャップ・アンド・トレード」とも呼ばれます。上限を超えた場合、高額の罰金や、将来の排出枠の剥奪といった処分が科されることもあります。
「排出権取引制度」は、国や地域、産業全体の排出量の抑制に役立ちます。また、企業にとって、排出削減がどれくらいの利益を生み出すのかを数値化し、予測しやすくなります。さらに、そもそもの排出量の算出には、該当データ収集が必要なため、排出源の把握にも役立ちます。
炭素税(カーボンタックス)とは?
炭素税(カーボンタックス)とは、企業の炭素排出に従量課金する仕組みです。そもそも、企業の排出に対してなぜ課税が適応されるのか?それは、排出が及ぼす影響に関して説明責任を負わせるはたらきがあるからです。
課税されることで、企業にとっては化石燃料消費(=炭素排出行動)などのコストが高まることになります。そのような状況は、企業が代替エネルギーやエネルギー効率向上を模索するきっかけにつながり、ひいては、炭素量の削減につながるのです。
「炭素税」「排出権取引」と「投融資先の排出量」の関係は?
課税の範囲にもよりますが、炭素税の導入が金融機関の金銭的負担になることもあるでしょう。しかし、「投融資先の排出量」の測定と抑制に先回りで取り組めば、将来起こり得る炭素税負担や排出枠超過への罰金を未然に防ぐことにつながります。

組織が脱炭素目標を定めるときのヒント
金融機関が脱炭素目標を設定する際、1. 状況の変化に応じて修正できるシステムをつくる、2. 複数の気候シナリオを加味する、3. 科学的裏付けのある手法を用いる、4. 進捗を測定できるシステムをつくる、5. 現実的な条件下で達成できるレベルである、などを意識することが大切です。
しかし、「投融資先の排出量」に現実的な削減目標を定めることは、口で言うほど簡単ではありません。目標が適当かどうか、判然としないことが多いためです。
脱炭素目標設定のためのより具体的なアクションプランを以下に示します。
- 複数の気候シナリオを加味し、短期と長期の目標を定める。
- 気象・気候災害などで物理的に被害を負うリスクと低炭素経済への移行に伴う変化が損失につながるリスク(物理的リスクと移行リスク)を考慮し、気候に対する目標自体のレジリエンスを確かめる。予想される潜在的な結果に基づき、目標を修正する手順を準備しておく。
- PCAFなど科学的裏付けのある手法を利用しながら、科学的根拠に基づく目標(SBT)を定める。炭素会計ツールを使って、監査や比較が可能なデータ生成をする。
- データ不足を推定で補う必要がある場合、PCAFのガイダンスに沿ってデータの質(DQ/データクオリティ)を評価する。
- 炭素会計ツールなどで生成した信頼度の高いデータなどに基づき、野心的ながらも対応可能で現実的な目標を定める。
- 組織としてのガバナンスを構築し、物理的リスクと移行リスクの両方を注視する。
排出削減に取り組まないポートフォリオ企業のために計画をつくる
ポートフォリオを構成する企業が、炭素排出量の削減に取り組まない(または、取り組めない)場合もあります。そんなとき、投融資元として、金融機関はどのように対応すべきでしょうか?
理想的な対応策としては、その企業と手を携え、ともに排出削減に取り組むことです。ポートフォリオ企業側からすれば、事業活動を脱炭素化することで、投融資元(金融機関)からの資金調達を維持できるというメリットがあります。また、投融資元(金融機関)側のメリットとしては、自組織が負担している「投融資先の排出量」とポートフォリオ企業側の排出量を合わせて減らせるため、ウィン・ウィンの取り組みになり得るということです。
投融資元(金融機関)は、ポートフォリオ構成企業や顧客に対して、どのような脱炭素アクションを提案できるでしょうか?おすすめのアクションを以下に示します。
- 炭素量測定ツール(ソフトウェア)の提供 やリソース、ガイダンスの供給を通じ、排出量の測定・管理を後押しする。
- 投融資を通じて排出削減を後押しする。
- 対象企業の排出削減予定を組み、段階的目標を定める。
- 排出量削減の明確な指針と定義を確立する。
- 自組織が「投融資先の排出量」の情報開示を通じて得たデータや知見を隠さず共有する。
- 専門家と協力し、低炭素への移行プロセスを洗練させながら、変化に応じてその都度修正を行う。
ほかにも、「カーボンニュートラル(炭素の排出量と吸収量が均衡した状態)」または「カーボンネガティブ(排出量を吸収量が上回った状態)」な資産に投資の比重を移すことも金融機関による排出量管理の方法の一つです。そうした資産への投資は、炭素排出量の削減への資金的な支援になるだけでなく、ポートフォリオの脱炭素化にも役立ちます。
さらに、排出削減をしない企業から投資を完全に引き揚げることも、一つの選択肢です。ただし、この方法では金融機関の排出削減にはなっても、ポートフォリオ構成企業に排出削減を促すことにはなりません。企業側が別の資金源を見つければ、それまでの通常運転が続けられるからです。
最後に、化石燃料産業や炭素排出が多い産業への今後の投融資を制限するか、徐々に減らすことも、金融機関が取れる有効な脱炭素アクションの一つとなるでしょう。
「投融資先の排出量」管理の始め方・続け方。
「投融資先の排出量」の管理に関して、1. ステークホルダーに情報や知識を共有すること、2. ポートフォリオの脱炭素化に向けて実行可能な予定を組むこと、3. 計画を絶えず改善すること、などが金融機関に求められています。ほかにも必要なことはありますが、とにかく算定をスタートさせ、社内協力者・賛同者を増やしていくことで、目標達成への取り組みを軌道に乗せることができるでしょう。
以下、金融機関が今すぐ取れるおすすめの脱炭素アクションを紹介します。
- 目標達成に欠かせない主要ステークホルダーを見定め、その役割や彼らに求めるべき行動を定める。
- 長期目標の中の中間目標を定める。
- 「投融資先の排出量」の削減計画について、主要ステークホルダーや従業員などに説明する。
- 金融アドバイザーや資産管理担当者など、顧客やポートフォリオ構成企業と接する従業員の脱炭素教育・研修を実施する。
- 炭素排出量の多いポートフォリオ構成企業や顧客とコミュニケーションを密にする。排出量の測定や削減を始めるよう背中を押す。
- 炭素排出量が最も多い「ホットスポット」への対応を最優先し、取り組みの効果を最大化する。
- 再生可能エネルギーやトランジションボンド(移行債)など、ポートフォリオの脱炭素化に寄与する「グリーン」投資の機会を研究する。
- 最初の測定の後、手に入るデータの量や質が上がってきたタイミングで、必要に応じて目標を再検討し、改善する。
- 自組織の脱炭素の取り組みについて、他者からフィードバックを受けられる仕組みをつくる。
- ポートフォリオ構成企業や顧客に直接影響する開示規則の最新情報に常に注意を払う。
「投融資先の排出量」管理において、オンライン証券大手のTDアメリトレードの取り組みは、ある意味での模範となり得るかもしれません。同社は2021年、エネルギー・発電事業者を通じた「投融資先の排出量」の削減目標を定め、2022年から排出量の測定・開示を開始しました。今後、エネルギー・発電事業者以外のセクターにも測定と目標設定の範囲を拡大していく計画です。
また、同社は自らの目標達成に役立つ手段も開発しています。たとえば、物理的リスクと移行リスクを視覚的に示し、その特定や評価に役立つヒートマップ・ツールを開発しています。

昨今、世界の大手銀行が化石燃料産業への投資を拡大したという状況があります。しかし一方で、銀行業界全体を見ると、2021年に画期的な出来事がありました。世界の銀行業務において、化石燃料企業への投資からの収益をグリーン関連債券の販売や融資からの収益が初めて上回ったのです。未来はこのまま変わるのでしょうか?金融機関は、環境を重視した事業にこそ収益の未来があり、今後はその認識に沿って資金を運用していくのでしょうか?
「投融資先の排出量」の報告・管理は、あらゆる金融機関にとって間違いなく重要です。そして、この取り組みを確実に進めるには、信頼できる実績と強い基盤を持った排出量算定・可視化・分析のクラウドサービスの利用が欠かせないでしょう。