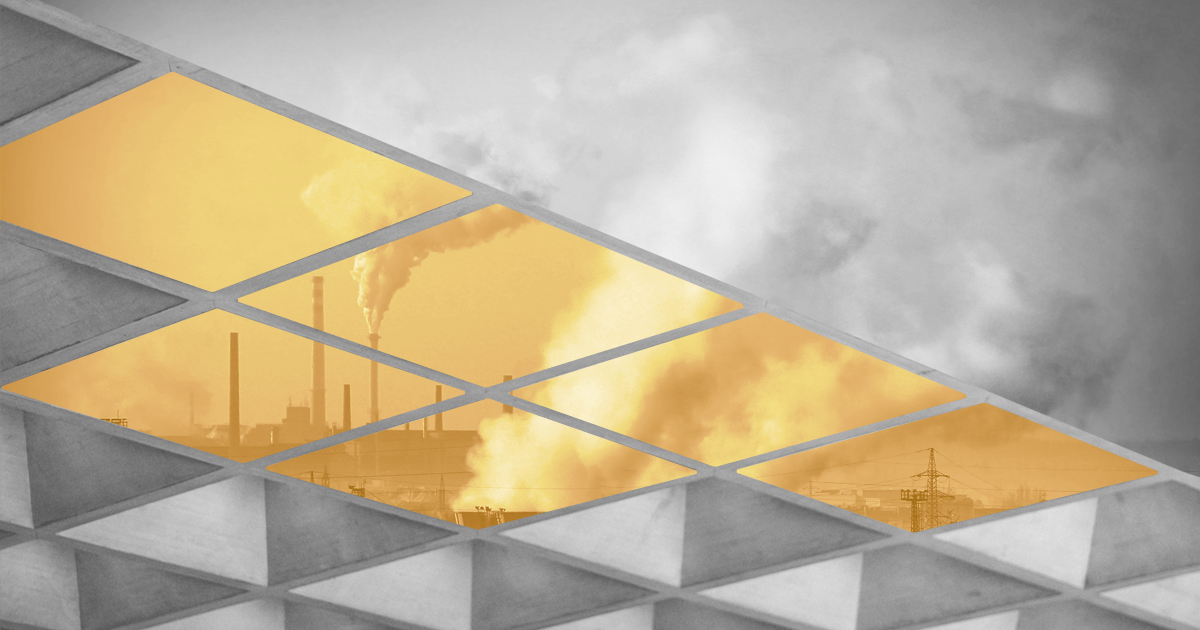「脱炭素経営って、具体的に何をすればいい?」
「世界の潮流から取り残されないか心配だ……」
このような思いを抱えている方は、多いのではないでしょうか。
脱炭素経営とは、企業活動で排出される温室効果ガスを削減し、地球温暖化防止に貢献しながら、持続的な成長を目指す経営のことです。

近年、気候変動対策の強化が世界的に進むなか、企業にとって脱炭素経営への転換が急務となっています。取り組まなければ、ビジネスチャンスを逃すだけでなく、存続すら危ぶまれる時代に突入しつつあります。
この記事では、脱炭素経営の概要から効果的な進め方まで、実務に役立つポイントを解説します。
最後までお読みいただくと、これからの時代を勝ち抜くための脱炭素経営の全体像が見えてくるはずです。
1. 脱炭素経営とは何か?

最初に脱炭素経営とは何か、基本事項から確認していきましょう。
- 脱炭素経営=気候変動対策の視点を織り込んだ企業経営のこと
- CO2排出量削減の取り組み例
- 脱炭素に取り組むうえで知っておきたい「温室効果ガス(GHG)」
- 3つの排出範囲で設定される具体的な対象領域
1-1. 脱炭素経営=気候変動対策の視点を織り込んだ企業経営のこと
まず「脱炭素経営」の定義について、ここでは環境省の説明を引用しましょう。
脱炭素経営とは、気候変動対策(≒脱炭素)の視点を織り込んだ企業経営のこと。
従来、企業の気候変動対策は、あくまでCSR活動の一環として行われることが多かったが、近年では、気候変動対策を自社の経営上の重要課題と捉え、全社を挙げて取り組む企業が大企業を中心に増加しております。
出典:環境省「脱炭素経営とは」
“脱炭素” は、「二酸化炭素(CO2)排出量をゼロにする」という意味です。
環境省の説明に「気候変動対策(≒脱炭素)」とあるように、地球温暖化の原因となるCO2をはじめとする排出量の抑制を経営の重点に据える企業経営を脱炭素経営といいます。
1-2. CO2排出量削減の取り組み例
脱炭素経営では、企業のバリューチェーン(製品の開発から製造・販売・廃棄に至るまでのあらゆる活動)全体におけるCO2排出量の削減を目指すのが特徴です。
イメージしやすいように、具体例を見てみましょう。
【CO2排出量削減の取り組み例】
- 生産工程の省エネ化:工場の製造ラインや設備の運用を見直し、エネルギー効率を高めて、CO2排出量を削減します。近年ではAIやIoTを活用した最適制御も採用されています。
- 再生可能エネルギーの導入:太陽光発電や風力発電など、再エネ由来の電力を積極的に活用します。再エネ設備を自社で導入して発電したり、再エネ由来の電力を購入したりして、化石燃料由来のCO2排出を抑制します。
- サプライチェーン全体での削減:調達する原材料や部品のサプライヤーにも、脱炭素化の取り組みを要請します。また、製品の輸送や物流の効率化を図り、サプライチェーン全体のCO2排出量を削減します。
- オフィスの省エネ化:照明のLED化や空調の最適化など、オフィスビルの省エネ対策を進めます。働き方改革と連動させたリモートワークの推進では、通勤に伴うCO2排出量の削減が期待できます。
1-3. 脱炭素に取り組むうえで知っておきたい「温室効果ガス(GHG)」
近年では地球温暖化対策として、CO2以外の温室効果ガス(GHG)削減の重要性も増しています。これに伴い、「脱炭素」という言葉がGHG全体を包括する概念として使われるケースも増えています。

CO2以外のGHGの例として、以下が挙げられます。
- メタン (CH4):天然ガスの主成分であり、家畜のげっぷ、水田、廃棄物などから排出されます。CO2よりも温室効果が高く、地球温暖化への影響が懸念されています。
- 一酸化二窒素 (N2O):肥料の使用、工業プロセス、燃料の燃焼などから排出されます。CO2の数百倍の温室効果を持つ強力なGHGです。
- ハイドロフルオロカーボン類 (HFCs):エアコンや冷蔵庫の冷媒、断熱材、消火剤などに使用されます。フロン類の代替物質として開発されましたが、CO2の数百〜数万倍の温室効果があります。
- パーフルオロカーボン 類(PFCs):半導体製造などの工業プロセスから排出されます。CO2の数千倍から数万倍の温室効果を持つガスです。
- 六フッ化硫黄 (SF6):電気設備の絶縁ガスなどに使用されます。CO2の2万倍以上の温室効果を持つ、最も強力なGHGのひとつです。
- 三フッ化窒素(NF3):半導体や液晶ディスプレイの製造工程で使用されます。CO2の約1.6万倍の温室効果があり、近年、排出量が増加しています。
※GHGについて、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事にてご確認ください。
GHG(温室効果ガス)
現代の脱炭素経営では、CO2を含むGHG全体の削減を目指すのが、基本スタンスとなります。
参考:環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
1-4. 3つの排出範囲で設定される具体的な対象領域
脱炭素経営では、GHG排出量を3つの範囲(スコープ)に分けて管理します。

【GHG排出量の3つの範囲(スコープ)】
- スコープ1(直接排出):自社の工場・オフィス・車両など、事業活動から直接排出されるGHGが対象です。化石燃料の使用量削減や、燃料転換などの対策が求められます。
- スコープ2(エネルギー起源の間接排出):自社が購入した電力や熱の使用に伴うGHG排出が対象です。再生可能エネルギー由来の電力調達を進めれば、スコープ2排出量を大幅に削減できます。
- スコープ3(その他の間接排出):原材料の調達から、製品の使用・廃棄まで、バリューチェーン全体で間接的に排出されるGHGが対象です。サプライヤーとの協働や、環境に配慮した商品設計などが必要となります。
脱炭素経営に取り組む企業は、スコープ1・2・3のそれぞれについて、排出量の算定と削減目標の設定を行う必要があります。スコープ1・2は自社内でコントロールしやすい一方、スコープ3はサプライチェーン全体での取り組みが脱炭素経営の鍵を握ります。
2. なぜいま脱炭素経営が最重要課題になっているのか?

近年、脱炭素経営が企業の最重要課題として浮上してきています。背景には、地球温暖化に対する危機感の高まりと、国内外における政策・ルール形成の加速があります。
以下のポイントを確認しておきましょう。
- 2015年のパリ協定
- TCFD・SBT・RE100の広がり
- 取り組まない企業が直面する経営リスク
2-1. 2015年のパリ協定
2015年に採択されたパリ協定は、世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力を追求することを目標に掲げました。
この目標達成に向けて、各国が2050年カーボンニュートラルの実現を宣言するなど、野心的なGHG削減目標を次々と打ち出しています。

出典:環境省 地球環境局「国内外の最近の動向について(報告)2024年2月14日」
このパリ協定以後、脱炭素に舵を切る動きが一気に加速したといえます。
日本は、2030年度にGHG排出量▲46%(2013年度比)、2050年にネットゼロを目指しています。この水準を、各企業も目指さなければなりません。
2-2. TCFD・SBT・RE100の広がり
脱炭素経営の世界的潮流を象徴するのが、TCFD・SBT・RE100といったイニシアチブ(主導的な取り組み)です。
脱炭素経営に取り組む際は、これらのイニシアチブへの参加を検討する企業が多いため、押さえておきたい知識です。以下でそれぞれ解説します。
(1)TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)
TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース)は、G20の要請を受けて金融安定理事会(FSB)によって設立された民間主導のタスクフォースです。
企業に対し、気候変動関連リスク・機会の財務的影響の開示を求めています。
2023年10月12日時点で、TCFDへの賛同企業・機関は世界全体で4,872に達し、日本からは1,445の企業・機関が賛同しています。

(2)SBT(Science Based Targets)
SBT(Science Based Targets)は、パリ協定が目指す「産業革命前からの気温上昇を1.5℃未満に抑制する」ことと整合した企業のGHG排出削減目標です。
2024年3月時点で、世界全体のSBT認定企業は4,779社、コミット中企業は2,926社に達し、前年同月と比較してそれぞれ112%、14%の増加となっています。

出典:環境省「SBT参加企業」
また、日本企業のSBT認定・コミット数は2024年3月までで988社にのぼります。

出典:環境省「SBT参加企業」
(3)RE100(Renewable Energy 100%)
RE100(Renewable Energy 100%)は、事業活動で使用する電力の100%を再生可能エネルギーで調達することを目指す国際的なイニシアチブです。
AppleやGoogleなど世界全体で428社(2024年3月)が参加しており、そのうち日本企業は86社となっています。

これらのイニシアチブへの参画は、もはや一部の先進的企業の話ではありません。
投資家や金融機関、消費者、就職活動中の学生まで、企業の脱炭素経営の取り組み度合いを測る指標として定着しつつあります。
2-3. 取り組まない企業が直面する経営リスク
脱炭素経営への対応の遅れは、企業の信頼や競争力の低下に直結しかねません。
【脱炭素経営を怠る企業の経営リスク】
- 市場シェアの低下:脱炭素に積極的な競合他社に顧客を奪われ、市場シェアを失うおそれがあります。環境配慮製品・サービスへのニーズが高まるなか、脱炭素の遅れは競争劣位に直結します。
- 資金調達コストの上昇:投資家が企業の脱炭素の取り組みを評価軸とするようになると、対応が不十分な企業は株価下落や、社債の利回り上昇などの資金調達コスト増に見舞われます。銀行融資の獲得にも影響が及ぶ可能性があります。
- サプライチェーンからの排除:サプライヤーにGHG削減を求める動きが強まれば、基準を満たせない企業は取引先から外される事態に陥ります。ビジネス機会の損失は避けられません。(*1)
- 優秀な人材の流出:脱炭素への意識が高い若手を中心に、温暖化対策に消極的な企業を敬遠する動きが広がっています。人材獲得力の低下は、イノベーション創出力など、企業の競争力全般の低下につながります。
- 社会的評価の低下:脱炭素の取り組み不足は、マスコミなどから厳しい批判の的となり、社会的評価を大きく毀損しかねません。ブランド価値の低下は、顧客離れや株価下落を招く可能性があります。
*1:取引先がスコープ3を含む野心的な取り組みを推進している場合には、サプライヤーに対しても脱炭素経営を求める場合があります。以下は環境省の資料からの抜粋です。

こうしたリスクは、未来の話ではなくなっています。脱炭素経営を先送りするほど、リスクは現実のものとなり、事業の継続そのものを脅かしかねない状況です。
3. 効果的な脱炭素経営の進め方

続いて、脱炭素経営を効果的に進めるための具体的なアクションについて見ていきます。
CO2削減目標の設定から、推進体制の構築まで、各ステップのポイントを確認しましょう。
- ステップ1:全社的な推進体制を構築する
- ステップ2:排出量の算定で見える化を実現する
- ステップ3:削減シナリオと計画を策定する
- ステップ4:具体的な削減を実行する
- ステップ5:PDCAを回して改善を重ねる
3-1. ステップ1:全社的な推進体制を構築する
1つめのステップは「全社的な推進体制を構築する」です。
脱炭素経営を全社的に浸透させ、継続的に高度化していくには、ガバナンス体制の構築が欠かせません。トップのリーダーシップのもと、全社一丸で取り組む体制を整備することが重要です。
【脱炭素経営の推進体制のポイント】
- トップ主導の経営戦略としての位置づけ:脱炭素経営を、トップ自らが重要性を語り続ける経営戦略の中核に位置づけます。シナリオ分析による事業インパクト評価も交えつつ、経営の重要議題として取締役会などで議論を重ねていきます。
- サステナビリティ委員会による全社横断の推進:CSO(最高戦略責任者)などを委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、全社横断での推進体制を構築します。各部門の施策を統括し、社内公募による脱炭素人材の育成や、外部人材の登用も進めて、実効性の高い推進の司令塔とします。
- ステークホルダーの信頼獲得に向けた情報開示の準備:自社の脱炭素経営の進捗を、統合報告書やサステナビリティレポートで積極的に開示します。前述のTCFD(*2)などのグローバル開示フレームワークへの対応を通じた情報開示についても、検討しましょう。
*2:TCFDの開示フレームワークとして、中小企業から大企業まで利用しやすいのは「CDP」です。

出典:環境省「【簡易版】TCFDシナリオ分析実践ガイド」を加工
CDPが提供する質問書に回答すると、その回答結果からCDPスコアが算出され、ステークホルダーへの情報開示に活用できます。詳しくは、以下の記事にてご確認ください。
CDP スコアとは
3-2. ステップ2:排出量の算定で見える化を実現する
2つめのステップは「排出量の算定で見える化を実現する」です。
脱炭素経営の具体的なアクションは、自社のGHG排出量を正確に把握することから始まります。
【排出量算定のポイント】
- スコープ1・2・3の網羅的な算定:工場や社用車などから直接排出されるスコープ1、電力や熱の使用に伴うスコープ2、サプライチェーン全体のスコープ3と、各排出量の算定範囲を明確にし、部門や取引先を巻き込んだデータ収集を行います。
- 継続的な見える化の実践:GHG排出量の見える化は、削減シナリオの立案や施策の効果測定に不可欠です。環境データの算定・集計を企業の基幹業務と位置づけ、継続的な実践体制を整備することが重要です。
上記を実践するためには、GHG排出量の算定を自動化するツールの導入をおすすめします。
スコープ1・2・3の計算は複雑で、計算に必要な値も随時アップデートされるため、Excelなどを使った手作業では非効率となるためです。

当社「Persefoni(パーセフォニ)」は、GHG管理プラットフォームのリーディングカンパニーであり、GHG排出量算定ツールを無償でご提供しています。
これから脱炭素経営に取り組む企業の方は、まずは無料で手軽にGHG排出量の算定をスタートしてみることをおすすめします。詳しくは以下のリンクよりご確認ください。
3-3. ステップ3:削減シナリオと計画を策定する
3つめのステップは「削減シナリオと計画を策定する」です。
排出量の算定結果を起点に、部門ごと、製品・サービスごとのGHG排出構造を分析し、中長期の削減シナリオを描きます。

【削減シナリオ策定のポイント】
- 意欲的かつ実現可能な目標設定:自社の排出量や財務状況を踏まえ、パリ協定と整合する野心的な長期目標を、前出のSBTなどの枠組みも活用して設定します。最新の脱炭素技術動向も見据えつつ、5年〜10年先の中期目標にブレークダウンすることが重要です。
- 事業部門別の削減計画とPDCAの構築:事業部門ごとに排出構造を分析し、各部門の特性を活かした主体的な削減計画の立案を促します。削減目標は経営計画にも落とし込み、統一基準で進捗管理するPDCAサイクルを全社で回していく体制を整備しましょう。
- シナリオに基づく最適な投資計画の立案:脱炭素設備への更新投資など、中長期の投資計画を練り上げます。投資による削減効果を定量的に見積もり、投資回収シナリオを複数描いたうえで、最適なタイミングでの投資実行計画を立案することがポイントです。
脱炭素シナリオは、トップのコミットメントのもと、環境部門だけでなく経営企画や財務部門とも連携して練り上げることが重要です。
具体的な目標設定の手順を知りたい場合は、環境省が提供している「中長期排出削減目標等設定マニュアル」がわかりやすくおすすめです。
3-4. ステップ4:具体的な削減を実行する
4つめのステップは「具体的な削減を実行する」です。
省エネ設備や再エネ設備への投資など、具体的な削減行動を計画的に実行に移すフェーズです。着実な削減の積み重ねが、脱炭素経営の基盤となります。
【脱炭素投資のステップ】
- 省エネと再エネ導入の両輪での推進:高効率設備への計画的な更新を進めます。同時に、太陽光発電の自家消費や再エネ電力の長期調達など、再エネ主力化の取り組みを両輪で推し進めることが重要です。
- サプライチェーン全体での削減の協働:原材料や部品のサプライヤーと協働し、サプライチェーン上流からのCO2排出削減を後押しします。サプライヤーの脱炭素化を支援することは、自社の競争力強化とスコープ3排出量削減の両方に寄与します。
- 現場の知見を活かした運用改善の継続:設備導入の計画段階から現場の知見を反映させ、省エネ効果を最大限に引き出します。導入後も、従業員一人ひとりの脱炭素行動を促しつつ、運用改善を継続的に行い、設備のエネルギー効率を高水準で維持し続けることが大切です。
設備投資の実行段階では、現場の協力がキーポイントです。現場の知見を投資計画の策定段階から反映させ、省エネ効果の最大化を目指していきましょう。
3-5. ステップ5:PDCAを回して改善を重ねる
5つめのステップは「PDCAを回して改善を重ねる」です。
ステップ1で構築した推進体制のもと、ステップ2の排出量の見える化、ステップ3の削減計画、ステップ4の具体的な削減施策の実行結果を、着実にPDCAサイクルで改善します。
役員会やサステナビリティ委員会で進捗を定期的に確認し、必要な対策を迅速に講じましょう。
【PDCAサイクル運用のポイント】
- 全社統一の進捗管理:事業部門ごとの削減施策の実施状況や効果を、統一された評価基準で管理します。スコープ1・2・3の排出量データと削減施策の相関を分析し、実効性の高い対策に注力します。
- バリューチェーン全体の最適化:上流の原材料調達から下流の製品使用・廃棄までの各段階で、取引先との協働による削減効果を検証します。優良事例はほかの取引先にも展開し、バリューチェーン全体の削減を加速させます。
- 投資効果の定量評価:高効率設備や再エネ設備への投資効果を、CO2削減量と投資回収の両面から評価します。評価結果は次の投資判断に反映させ、より費用対効果の高い削減施策の実行につなげます。
PDCAを通じて得られた知見は、気候変動のリスクと機会の分析にも活用し、TCFDなどの開示フレームワークに沿った情報発信の質も高めていきましょう。経営戦略の進化と連動させながら、脱炭素経営の高度化を図っていきます。
4. 脱炭素経営に着手する際のポイント

最後に、脱炭素経営に着手する際、あらかじめ押さえておきたい2つのポイントをお伝えします。
1. 自社に適したプラットフォームを導入する
2. 社内専門人材の育成に取り組む
4-1. 自社に適したプラットフォームを導入する
1つめのポイントは「自社に適したプラットフォームを導入する」です。
先ほど、GHG排出量算定ツールについてご紹介しました。
脱炭素経営を本格化していくプロセスでは、より高度な見える化・削減・報告ができるサービスの利用が、鍵となります。
たとえば、パーセフォニのサービスには、AI機能で炭素会計と脱炭素化をより効率的に実現する「パーセフォニAI機能」を搭載しています。

【パーセフォニAIの詳細】
- パーセフォニ・コパイロット:パーセフォニ・コパイロットは、パーセフォニの大規模言語モデル(LLM)上に構築されたAIシステムです。チャット形式のインターフェースで、GHG排出量の算定・報告に関する技術的な専門知識を提供します。
- 異常値検知:GHG排出量を厳密に算定するためには、数千・数百万のデータが必要です。パーセフォニAIは、電力消費量などの主要なデータを対象とした、統計的異常検知機能を搭載しています。
- 自然言語で利用可能な排出係数マッピング:パーセフォニAIは、財務データを解析し、その中から購買データを抽出し、該当LCA・該当排出係数を自動マッピングします(近日リリース予定)。
プラットフォームの導入は、脱炭素経営の基盤づくりの重要ポイントです。世界の数多くの一流企業に選ばれているパーセフォニのデモは、お気軽にこちらのページよりお問い合わせください。
4-2. 社内専門人材の育成に取り組む
2つめのポイントは「社内専門人材の育成に取り組む」です。
脱炭素経営を力強く牽引するには、社内の専門人材の育成と、実効性ある推進体制の構築が鍵となります。
【脱炭素人材の育成の取り組み】
- 人材育成プログラムの整備:脱炭素に関する専門知識やスキルを持った人材の裾野を広げるには、体系的な人材育成プログラムの整備が欠かせません。外部研修の活用や、若手人材のジョブローテーションによる経験の蓄積など、戦略的な育成施策を講じましょう。
- 社外との人材交流の活性化:社内人材の視野を広げるためにも、同業他社や異業種、アカデミア(大学などの研究機関)などとの人材交流の機会を設けることが有効です。社外の知見に触れることは、新たな発想を生み出し、取り組みの質の向上につながります。
- インセンティブ設計:脱炭素の進捗状況を人事評価に組み込むなど、従業員のモチベーション向上につながるインセンティブ設計も重要な検討課題です。脱炭素を自分事化し、積極的に取り組む風土の醸成を後押しする仕組みづくりを進めましょう。
脱炭素人材の育成と体制の整備には、一定の期間を要します。中長期的な視点に立ち、人材の発掘・育成と組織づくりに計画的に取り組むことが重要です。
トップのリーダーシップのもと、人材と組織の両輪がうまく噛み合ってこそ、脱炭素経営の真価が発揮されるといえるでしょう。
5. まとめ
本記事では「脱炭素経営」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。
最初に脱炭素経営の基本事項として、以下を解説しました。
- 気候変動対策(≒脱炭素)の視点を織り込んだ企業経営のこと
- CO2をはじめとする温室効果ガス排出量削減を、バリューチェーン全体で進める取り組み
- CO2以外のメタンや一酸化二窒素なども視野に入れつつ、排出量の算定・削減を行う
- 自社の排出量をスコープ1・2・3の3つの範囲に分けて把握・管理する
なぜいま脱炭素経営が最重要課題になっているのか、ポイントは以下のとおりです。
- 2015年のパリ協定を受けた各国の野心的なGHG削減目標の表明
- TCFD、SBT、RE100など、企業の脱炭素経営を促す国際的イニシアチブの広がり
- 投資家や消費者など、ステークホルダーからの脱炭素経営を求める圧力の高まり
- 脱炭素経営に取り組まない企業が直面する、市場シェア低下などの経営リスク
効果的な脱炭素経営の進め方を4つのステップでご紹介しました。
- ステップ1:全社的な推進体制を構築する
- ステップ2:排出量の算定で見える化を実現する
- ステップ3:削減シナリオと計画を策定する
- ステップ4:具体的な削減を実行する
- ステップ5:PDCAを回して改善を重ねる
脱炭素経営に着手する際のポイントは以下のとおりです。
- データを効率的に収集・管理できる、適切なプラットフォームを導入する
- 人材育成プログラムの整備など、脱炭素を牽引する社内人材を戦略的に育成する
自社の事業環境に適した形で脱炭素経営を進めることが、すべての企業に求められています。早期に一歩を踏み出し、脱炭素経営のフロントランナーとなることが、これからの時代を勝ち抜く鍵となるでしょう。