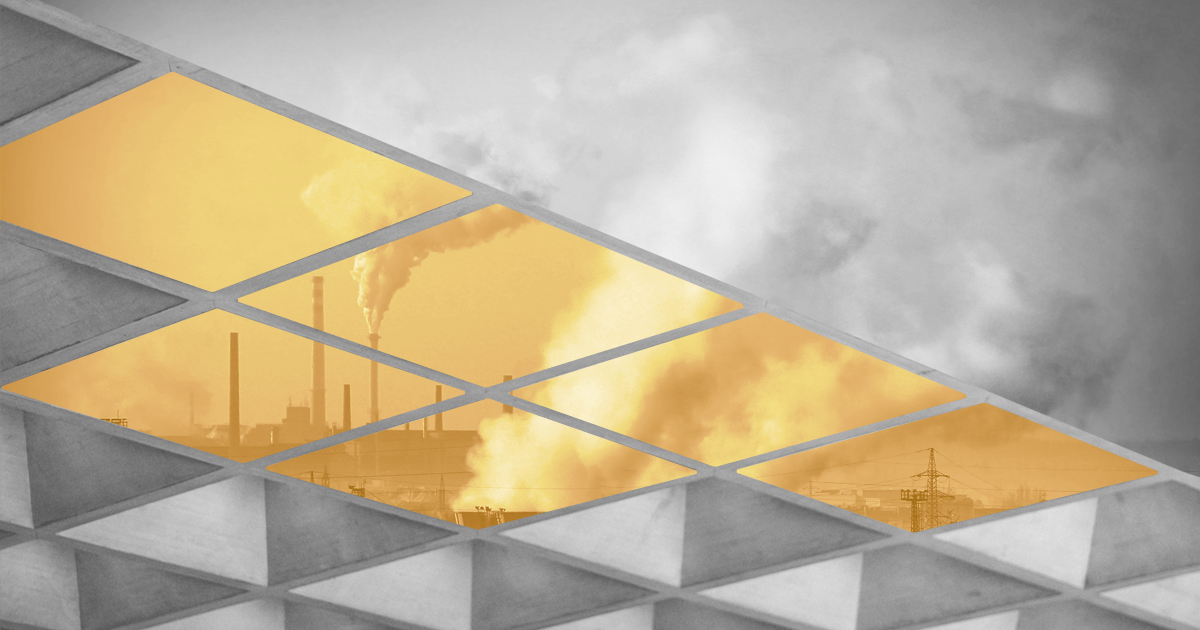「CDPスコアって何だろう?企業価値にどう関係するの?」
このような疑問をお持ちではないでしょうか。
CDPスコアとは、一言でいうと、企業の環境情報開示と取り組みを評価するグローバルな指標です。環境問題への関心が高まるなか、「CDPスコア」に注目が集まっています。

CDPスコアの高低は、機関投資家の投資判断に直結するため、企業価値を大きく左右します。一方、中小企業にとっても、取引先からの要請や金融機関からの評価など、CDPスコアの重要性が増しています。
本記事では、CDPの概要から、CDPスコアの仕組みや情報開示の進め方まで、体系的に解説します。
CDPスコアとは何かを知り、自社の取り組みに反映させるためにお役立てください。
1. CDPの概要
最初に、CDPスコアの「CDP」とは何か、基本的な事項から確認していきましょう。
1-1. CDP=イギリスの国際的な環境非営利団体の名称
「CDP」は、2000年にイギリスで設立された国際的な環境非営利団体(NGO)で、「人々と地球にとって、健全で豊かな経済を保つ」ことを目的に活動しています。

設立当初は「Carbon Disclosure Project(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト:炭素情報開示プロジェクト)」の名称で、気候変動対策に焦点を当てていました。現在では森林や水資源など、幅広い環境課題にも取り組んでいます。
その結果、「CDP」という略称が定着し、環境関連情報の開示と評価を促進する存在として、国際的な認知を得ています。
参考:CDP「リーディングテナント行動方針に係るセミナー CDPからの情報提供」
1-2. CDPの主要な活動内容
CDPの主要な活動内容として、以下が挙げられます。
【CDPの主要な活動内容】
- 企業の環境情報開示の要請:世界の時価総額上位企業などに対し、気候変動・水セキュリティ・フォレストなどに関する質問書を送付し、情報開示を求めています。
- 各国政府との連携:各国政府や政策立案者に対して、データ・分析結果を提供し、パリ協定目標達成に向けた政策形成を後押ししています。
- 企業の脱炭素化促進:SBT(パリ協定が求める水準と整合した、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標)を通じ、各企業では科学的知見に基づく中長期の排出削減目標の設定を進めています。
- 環境情報の分析と評価:企業から開示された環境情報を分析・評価し、投資家などに対してレポートを提供しています。
※補足:パリ協定やSBTについて基礎情報が必要な方は、官公庁サイトの以下ページがわかりやすくおすすめです。
今さら聞けない「パリ協定」 ~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?(資源エネルギー庁)
SBT(Science Based Targets)について(環境省)
上記のCDPの活動のうち、質問書の回答内容を分析して評価を数値化したものが「CDPスコア」です。CDPスコアの詳細は以下に続きます。
2. CDPスコアの仕組み

「CDPスコア」とは、各企業のCDP質問書の回答内容を評価したものです。以下で具体的に確認していきましょう。
- CDP質問書の回答者と要請者
- 質問書は3テーマから1つに統合(環境テーマ別にモジュール構成)
- CDPスコアの仕組み
2-1. CDP質問書の回答者と要請者
CDPは、毎年、世界の時価総額上位企業に対してCDPスコア算出のもととなる質問書を直接送付し、情報開示を依頼しています。
一方、CDPは情報開示のプラットフォーム提供者でもあります。

出典:CDP「リーディングテナント行動方針に係るセミナー CDPからの情報提供」
情報開示の要請者(金融機関やサプライチェーンの購買企業など)と、要請を受けた企業や自主的に回答する企業が情報共有できるプラットフォームを、CDPが運営しています。
【情報開示の流れ】
- 要請者(金融機関や購買企業など)がCDPを通じて、回答を希望する企業リストを提出します。
- CDPは、そのリストに基づいて企業に質問書を送付します。
- 企業は質問書に回答し、CDPに提出します。
- CDPは回答内容を分析・評価し、スコアを算出します。
- 要請者は、CDPのプラットフォームを通じて、企業の回答内容やスコアを確認できます。
よって、CDP質問書の回答者には、以下の3パターンがあります。
- CDPから直接要請を受けた企業
- 金融機関や購買企業から要請を受けた企業
- 自主的に回答する企業
2-2. 質問書は3テーマから1つに統合(環境テーマ別にモジュール構成)
2023年まで、CDP質問書は気候変動・水セキュリティ・フォレストの3テーマに分かれていました。

出典:CDP「リーディングテナント行動方針に係るセミナー CDPからの情報提供 2024年2月6日」
【CDP質問書の3つのテーマ】
- 気候変動:GHG(温室効果ガス)排出量の算定・報告、排出量削減の取り組み、リスク認識、ガバナンス体制などについて質問されます。
- 水セキュリティ:水リスクの評価、水使用量の測定・モニタリング、水リスク管理の体制、水ストレス地域での取水量などについて質問されます。
- フォレスト:森林破壊リスクの特定、森林由来原材料のトレーサビリティ確保、サプライヤーとの協働、森林破壊ゼロを目指す方針の有無などについて質問されます。
2024年には、これらが1つのコーポレート質問書に集約され、1度の情報開示で複数の環境課題に関する情報を回答できるように変更されました。

出典:CDP「[企業向け]CDP概要と回答の進め方 2024年5月」
質問書の中では「気候変動・フォレスト・水・プラスチック・生物多様性」の環境テーマ別にモジュールが設けられています。
つまり、従来の「気候変動・フォレスト・水」の3テーマがなくなったわけではなく、モジュールとして再構成され、新たに「プラスチック」と「生物多様性」が加わっています。
最新の質問書はCDPのWebサイトの「Guidance for companies」より確認できます。
2-3. CDPスコアの仕組み
企業から提出されたCDP質問書の回答は、4つの段階で評価されます。最終的には、8段階(A~D-)のスコアが付与されます。

【4つの評価段階】
- 情報開示: まず、企業が環境に関する情報をどれだけ詳しく報告できているかを評価します。
- 認識: 次に、企業が自社の事業活動と環境問題との関係をどれだけ理解しているかを評価します。ただし、この段階では環境問題への対策を実行しているかどうかは評価の対象ではありません。
- マネジメント: さらに、企業が環境への影響を理解したうえで、具体的な対策を行っているかを評価します。環境への影響を適切に管理できているかどうかをチェックし、その分野でリーダーとなるような取り組みを行っているかも確認します。
- リーダーシップ: 最後に、企業が環境保全において業界の模範となるような取り組みを行っているかを評価します。これは、CDPが協働している機関によって策定されたベストプラクティス(優れた取り組み事例)に基づいて評価されます。実際に、環境対策で先進的な企業が実践している取り組みが基準となっています。
より詳しくは、CDP資料の「CDP2024コーポレート完全版質問書スコアリングイントロダクション」にてご確認ください。
3. CDPを通じた情報開示の現況

続いて、CDPを通じた情報開示がどの程度進んでいるのか、実際の状況を確認しましょう。
1. CDPを通じた開示企業数(2023年)
2. CDP 2023 Aリストの企業例
3-1. CDPを通じた開示企業数(2023年)
CDPの資料によれば、日本における2023年開示企業数は約2,000社(プライム市場上場企業1,100社を含む)にのぼります。

出典:CDP「[企業向け]CDP概要と回答の進め方 2024年5月」
全世界では23,000社以上となり、前年比の増加率は24%となっています。2025年以降も増加していくことが推測されます。
2023年の開示企業数(日本)の詳細は、以下のとおりです。
【CDP 2023 日本企業の開示企業数(署名機関、顧客企業・機関からの要請)】

出典:CDP「JP企業スコア - 2023」をもとに作成しました(現在では見えなくなっています)
3-2. CDP 2023 Aリストの企業例
本記事執筆時点では、2023年のCDPスコアが公表されている最新版です。
注意点として、前述のとおり、2024年より質問書やスコア算定の大幅改訂がありました。
2023年のAリストは「気候変動」「フォレスト」「水セキュリティ」の3つのテーマに対して、“A ・A-・B・B-・C・C-・D・D-” の8段階でスコアリングが行われています。CDP 2023 Aリストに認定された日本企業数は、以下のとおりです。

出典:CDP「JP企業スコア - 2023」をもとに作成しました(現在では見えなくなっています)
このうち、3つのテーマでAスコアを獲得したトリプルAの企業は、以下の2社です。
- 花王株式会社
- 積水ハウス株式会社
その他、ダブルA(日清オイリオグループ、ユニ・チャーム他)・シングルA(王子ホールディングス、カゴメ他)の企業リストは、CDPサイトの「JP企業スコア」にて確認できます(執筆時は確認できましたが、現在は確認できなくなっています)。
また、Aリスト企業のトップエグゼクティブのスピーチ動画が「CDP AWARDS JAPAN 2024 Company videos - CDP」に掲載されており、取り組みの参考になります。
4. CDPスコアで高評価を獲得するメリット

「自社でも、CDP質問書への回答に取り組むべきだろうか?」
と検討中の方もいるでしょう。
その検討材料として、CDPスコアで高評価を獲得すると、どのようなメリットがあるのか、整理しておきましょう。
- ESG投資の呼び込みに有利になる
- 金融機関やサプライチェーン購買企業からの評価に直結する
- ステークホルダーとの信頼関係構築に寄与する
- 自社のサステナビリティ進捗の把握に役立つ
4-1. ESG投資の呼び込みに有利になる
1つめのメリットは「ESG投資の呼び込みに有利になる」です。
ESGとは、Environment(環境)・Social(社会)・Governance(ガバナンス)の頭文字を取った略語です。企業を財務情報だけで判断するのではなく、これらの非財務情報も考慮して、企業の持続可能性を評価する考え方がESGです。
CDPの高スコア企業は、世界の機関投資家から注目され、ESG投資を呼び込みやすい立場にあります。
【CDPスコアとESG投資の関係】
- ESG指数の構成銘柄に採用:FTSE4Good IndexやDow Jones Sustainability Indexなどの著名なESG指数の構成銘柄の選定において、CDPスコアが活用されるケースが増えています。高スコアはESG指数組み入れの有力な判断材料となります。
- グリーンボンドの発行体として選好:グリーンボンド(環境問題の解決に資する事業に使途を限定して発行される債券)などのESG債の発行体選定の際、CDPスコアがひとつの評価基準となる場合があります。高スコアは資金調達面での追い風になります。
- ESG対話のきっかけに:CDP回答とスコアは、機関投資家とのESG対話において有効な議論材料となります。高スコアは投資家からのエンゲージメントを促進する呼び水となり得ます。
企業の環境対応力を示す客観的な指標として、CDPスコアは投資家から高く評価されていることがわかります。
環境関連の非財務情報開示の充実は、中長期の企業価値向上に直結する重要な経営課題です。
4-2. 金融機関やサプライチェーン購買企業からの評価に直結する
2つめのメリットは「金融機関やサプライチェーン購買企業からの評価に直結する」です。
1つめのメリットだけを見ると、CDPスコアは上場企業・大企業にしか関係のない話と感じるかもしれません。
しかしながら近年、金融機関は融資先企業の選定にあたり、非財務面のリスク評価を重視する傾向にあります。サプライチェーンにおける購買企業も、取引先のESG対応状況をより重視するようになってきました。
【金融機関・購買企業とCDPスコアの関係】
- 融資やコーポレートファイナンスの判断材料:銀行は与信判断や融資条件の設定にあたり、CDPスコアを参考にするケースが増えています。高スコアは有利な融資条件の獲得や金利の引き下げにつながる可能性があります。
- サプライヤー評価の指標として活用:CDPサプライチェーンプログラムに参加する大手購買企業は、サプライヤーの選定・評価にCDPスコアを用いるケースがあります。高スコアはサプライチェーンでの取引機会の拡大や取引条件の改善に寄与します。
このように、金融機関やサプライチェーンの購買企業は、取引先のCDPスコアを重要な評価指標と捉えるようになっています。
高スコアは、企業の金融面・ビジネス面での強みにつながる可能性が高まっているのです。
4-3. ステークホルダーとの信頼関係構築に寄与する
3つめのメリットは「ステークホルダーとの信頼関係構築に寄与する」です。
CDPスコアの向上は、投資家だけでなく、さまざまなステークホルダーとの信頼関係構築にも役立ちます。
【CDPスコアとステークホルダーの関係】
- 顧客との関係強化:CDP高スコア企業は、環境意識の高い消費者から選好されます。高スコアはブランド価値向上とグリーン購入(環境に配慮した製品の優先的な購入)の促進につながります。
- 優秀な人材の獲得:CDPスコアは、就職先を選ぶ学生など将来の人材から注目される指標です。高スコアは、環境に配慮する優秀な人材の獲得に役立ちます。
- 地域社会の信頼獲得:CDP高スコア企業は、地域社会から「良き企業市民」として評価される傾向にあります。高スコアは操業地域からの信頼獲得に貢献します。
ステークホルダーからの信頼は、企業の社会的評価を向上させる源泉となります。
CDPを通じて環境対応の実効性を示すことは、多様なステークホルダーの支持を獲得することにつながるのです。
4-4. 自社のサステナビリティ進捗の把握に役立つ
4つめのメリットは「自社のサステナビリティ進捗の把握に役立つ」です。
CDPスコアの推移は、自社の環境分野のサステナビリティの進捗度合いを測る物差しとしても有効です。
【CDPスコアとサステナビリティ進捗の関係】
- 環境目標の達成度合いの確認:CDPスコアの推移を追跡すれば、自社の中長期環境目標の達成度合いを客観的に把握できます。スコアの向上は目標達成に向けた着実な前進を意味します。
- 他社との比較によるベンチマーク:同業他社とのスコア比較により、業界内での自社の相対的な位置づけや改善余地を特定できます。競合他社に後れを取っていないかの確認に役立ちます。
- 環境課題の優先順位づけ:CDP質問書の各設問への回答状況から、自社の環境対応上の強みと弱みが浮き彫りになります。対応が不十分な領域を特定し、課題解決の優先順位づけをするために有益です。
このように、CDPスコアを活用すると、自社のサステナビリティ戦略のPDCAサイクルを効果的に回していくことが可能です。
環境目標と実績の進捗管理に、CDPを戦略的に活用している企業が増えている背景には、こうした背景があります。
以上、4つのメリットを解説しました。

続いて以下では、情報開示の進め方について見ていきましょう。
5. CDPスコアの情報開示の進め方

「初めて、CDPスコアの情報開示に取り組みたい」という場合、何をどのように進めればよいのでしょうか。5つのステップに分けて、見ていきましょう。
- GHG排出量算定ツールを導入する
- 経営層のコミットメントと体制構築を進める
- 現状分析をもとに中長期目標を設定する
- 実行計画を策定し削減施策を推進する
- 実績を積極的に開示する
5-1. GHG排出量算定ツールを導入する
1つめのステップは「GHG排出量算定ツールを導入する」です。
CDPスコアの情報開示を進めるうえでは、まずGHG排出量の算定が不可欠です。
GHGとは、CO2をはじめとする温室効果ガスのことです。CDP質問書の気候変動モジュールでは、以下の排出量に関する情報開示が求められます。
【CDP質問書で情報開示が必要なGHG排出量】
- スコープ1:事業者が直接排出するGHG排出量(燃料の燃焼、工業プロセスなど)
- スコープ2:購入した電力、熱、蒸気などの使用に伴う間接排出量
- スコープ3:事業者のバリューチェーン全体におけるその他の間接排出量(サプライヤーからの調達、製品の使用、廃棄など)
上記は、Excelなどを駆使して手作業でも算定できます。しかしながら、データ収集・排出係数の調査・排出量の計算・スコープ別の集計……、という具合に、多大な労力が必要です。
よって、まずはGHG排出量算定ツールの導入が現実的な選択肢となります。

当社「Persefoni(パーセフォニ)」は、GHG排出量算定プラットフォームのリーディングカンパニーであり、GHG排出量算定ツールを無償でご提供しています。
将来的に、より本格的なツールを導入する場合でも、まずは無償版で使用感を確かめてみると、賢明な判断ができます。以下のリンクより詳細をご確認ください。
5-2. 経営層のコミットメントと体制構築を進める
2つめのステップは「経営層のコミットメントと体制構築を進める」です。
CDPスコアの開示範囲は多岐にわたるため、トップのリーダーシップのもと、関連部門が一丸となって取り組む必要があります。
【体制構築の取り組み例】
- CDP対応の役員の任命:CDPを含むサステナビリティ分野を統括する専任の役員を置くことが有効です。経営会議などで定期的に報告してもらい、継続的な推進力を担保します。
- 環境目標の経営計画への組み込み:中長期のGHG削減目標などを経営計画の一部に組み入れます。年度計画のKPIにも落とし込み、着実な達成を目指します。
- サステナビリティ委員会の設置:経営層主導のサステナビリティ委員会を設け、CDP対応の進捗管理を行います。関連部門の責任者クラスで構成し、全社横断の体制を整備します。
- 報酬との連動:CDPスコアの向上度合いを、業績連動報酬の指標に組み込みます。経営層のコミットメント強化と、社内の意識喚起を同時に図ります。
こうした施策により、CDP対応を企業経営の重点テーマとして位置づけ、継続的な取り組みを支えるガバナンスを構築していきましょう。
5-3. 現状分析をもとに中長期目標を設定する
3つめのステップは「現状分析をもとに中長期目標を設定する」です。
CDP質問書では、企業の気候変動対策に関する中長期ビジョンと具体的な目標値が求められます。自社の現状を定量的に把握し、その分析結果をもとに意欲的な目標を設定することが大切です。
【中長期目標の設定プロセス】
- 現状の排出量の分析:事業所別・製品別・スコープ別など、さまざまな切り口でGHG排出量を可視化します。排出量が多い箇所を特定し、削減ポテンシャルを評価します。
- 同業他社とのベンチマーク:業界内での自社のポジショニングを確認します。先行企業の目標値や削減施策を分析し、自社の目標設定の参考にします。
- SBTなどの目標設定イニシアチブの活用:前出のSBTなど、パリ協定と整合した削減目標を設定するためのイニシアチブがあります。その基準と手法論を活用し、野心的な目標設定を目指します。
- 長期ビジョンとのつながりの明確化:企業理念や長期ビジョンとのつながりを示し、環境目標の位置づけを明確にします。気候変動対策を企業の存在意義として社内外に打ち出します。
現状をふまえ、意欲的な目標を掲げることは、企業姿勢を示すうえでも重要です。自社の目指す将来像に即した目標設定を進めていきましょう。
5-4. 実行計画を策定し削減施策を推進する
4つめのステップは「実行計画を策定し削減施策を推進する」です。
中長期目標の達成には、確実な実行計画の策定と推進が不可欠です。各部門の責任者が主体となり、目標達成に向けたロードマップを描きましょう。
【中長期目標達成に向けた実行計画のポイント】
- 削減施策の具体化:目標達成のために導入を検討する省エネ設備や再エネ調達などの削減施策を具体的にリストアップします。各施策の削減ポテンシャルと投資対効果を試算し、優先順位をつけます。
- 進捗管理指標の設定:各施策について、定量的なマイルストーンを設けます。単年度の削減量などの実績値を部門ごとにモニタリングし、PDCAサイクルを回します。
- 投資計画の策定:省エネや再エネ関連の投資計画を年度予算や中期経営計画に組み込みます。計画的な投資により、大幅な排出削減を実現します。
- 従業員の意識啓発・教育:従業員一人ひとりが気候変動対策の当事者意識を持てるよう、継続的な啓発活動や教育を実施します。部門横断的なプロジェクトチームを立ち上げるなどして、ボトムアップの活動を促します。
このように、全社を挙げて削減施策のPDCAを回し、着実な削減実績を重ねていくことが大切です。部門間の連携を図り、企業全体でベクトルを合わせた取り組みを進めていきます。
5-5. 実績を積極的に開示する
5つめのステップは「実績を積極的に開示する」です。
CDP質問書への回答を通じて、自社の環境に対する取り組み実績や目標を開示し、ステークホルダーに伝えていきましょう。
【環境情報開示の深化に向けた取り組み】
- CDP回答の継続的改善:毎年、CDPへの回答を継続します。前年のCDPフィードバックをもとに、回答の深掘りや精緻化を進めます。着実にレベルアップを重ね、進化し続ける姿勢を対外的に示していきます。
- 統合報告書などでの言及:統合報告書、サステナビリティレポートなどの開示媒体でも、CDP回答との整合性を保ちつつ、自社の環境対策について積極的に紹介します。CDP評価の伸長度合いも盛り込みます。
- Webサイトでのタイムリーな発信:CDP回答で網羅的なデータを開示しつつ、自社Webサイトではタイムリーな情報発信を心がけます。最新の取り組み事例などを随時公開し、環境コミュニケーションの充実を図ります。
- 環境関連の表彰制度への応募:CDP以外の環境関連の表彰制度にも応募します。受賞実績を積み重ね、ステークホルダーからの評価を高めます。
このように、CDPへの回答をきっかけとして、情報開示の質と量を高めていくことを目指しましょう。
5-6. 補足:中小企業向けのSME質問書
最後に補足として、CDPは、大企業向けの「コーポレート完全版質問書」に加えて、中小企業向けの「コーポレート SME (中小企業)版質問書」を提供しています。
SME版は、完全版よりも質問数が少なく、より簡潔なフォーマットで回答できるようになっています。
具体的な質問書の内容などは、CDPの公式サイトにて最新版をご確認ください。
6. まとめ
本記事では「CDPスコアとは?」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。
最初に、CDPの概要として以下を解説しました。
- CDPは環境問題に取り組む国際NGOであり、企業の環境情報開示を促進している
- 企業の環境情報開示レベルと取り組み状況を評価し、CDP スコアとして公表している
- CDP スコアは、投資家やサプライチェーン企業の投資判断や取引先選定に影響を与えている
CDPスコアの仕組みは以下のとおりです。
- 「気候変動・フォレスト・水・プラスチック・生物多様性」といったテーマについてCDP質問書で回答する
- 質問書の回答内容は、情報開示・認識・マネジメント・リーダーシップの4つのレベルで採点される
- 最終スコアは、A・A-・B・B-・C・C-・D・D-の8段階で評価される
CDPを通じた情報開示の現況は以下のとおりです。
- 日本における開示企業数は約2,000社、世界全体では23,000社以上にのぼる(2023年)
- CDP 2023 Aリストには、気候変動で112社、フォレストで7社、水セキュリティで36社の日本企業が選定された
- 3つのテーマすべてでAスコアを獲得したトリプルAは、花王と積水ハウスの2社である
CDPスコアで高評価を獲得するメリットは以下のとおりです。
- ESG投資の呼び込みに有利になる
- 金融機関やサプライチェーン購買企業からの評価に直結する
- ステークホルダーとの信頼関係構築に寄与する
- 自社のサステナビリティ進捗の把握に役立つ
CDPスコアの情報開示の進め方として、以下を解説しました。
- GHG排出量算定ツールを導入する
- 経営層のコミットメントと体制構築を進める
- 現状分析をもとに中長期目標を設定する
- 実行計画を策定し削減施策を推進する
- 実績を積極的に開示する
企業がCDPスコアを戦略的に活用し、環境情報開示の高度化を図ることは、ESG時代の企業価値向上に直結する重要な経営課題です。本記事をきっかけに、環境課題にも強靭な企業体質の構築を目指していただければと思います。