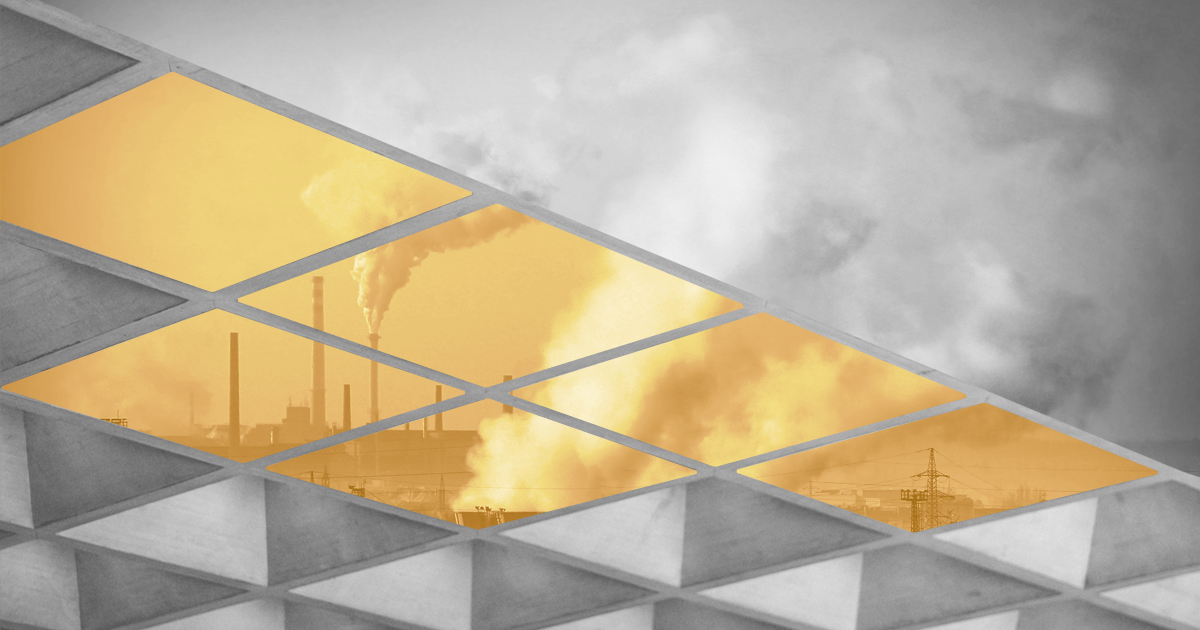概要
気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)は、企業や金融機関に対して、ステークホルダー(投資家、貸付業者、保険会社、他)に向けた気候関連のリスクと機会の開示をより包括的で一貫性のある報告にするための提言を行っています。 例えば、気候変動に関連する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つを基本にした開示を提言しています。 TCFDフレームワークは、財務面から気候関連のリスクと機会を評価・報告するためのツールとして世界中の企業や金融機関に広く採用されています。
TCFD(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース)は2015年、企業や金融機関に気候変動に関わる財務リスクを踏まえた対応や適応を促すことを目的に金融安定理事会(FSB)によって設立されました。 FSBがTCFDに与えた任務は、金融市場が気候関連のリスクと機会を評価し、その財務的影響を検討するために必要とする情報の特定です。 投資家、貸付業者、保険会社に必要な情報もこれに含まれます。
この任務を果たすべく、TCFDは2017年の「Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures(気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言 最終報告書)」を皮切りに情報開示の推奨事項や補助ガイダンス、諸原則を公表してきました。 これらの提言や手引きは、情報に基づく意思決定を促し、気候変動が金融市場や財務に及ぼす影響を主要ステークホルダーや投資家が理解するのを助け、気候関連リスクの情報開示のあり方を企業に示しています。
TCFDに賛同し、実施を推進する企業や金融機関は現時点で3,000を超えています。 G20やIFRS(国際会計基準)財団などの主要国や組織もTCFDフレームワークを情報開示規定のベースとしています。
米国では、 証券取引委員会(SEC)が上場会社を対象にした気候関連情報開示の義務化に向けて準備を進めています。 規則案が可決されると、 ニュージーランドやシンガポールなどの国々と並び、米国でもTCFDを含む世界的に認められた基準に沿った気候関連情報開示が大規模上場企業に義務付けられることになります。 TCFDフレームワークの理解はどの組織にとっても重要ですが、炭素会計(GHG排出量の算定・報告)を導入したばかりであれば特に慎重な対応が必要です。
このガイドは、TCFDとは?に始まり、TCFDの提言内容や今後に備えて知っておきたい知識など必要なポイントを網羅しています。 ここではTCFDのフレームワークとその他重要情報の要点を取り上げていますが、TCFDの公式ウェブサイトにアクセスするとより詳しい情報を入手できます。
TCFDの目的
TCFDの目的は、企業や金融機関に気候関連のリスクと機会を踏まえたより精度の高い戦略判断を促すことです。 TCFDが示すガイダンスも、気候政策や新技術の進展など気候変動に関わる急速な変化に後れを取らないための重要な情報源です。
企業がTCFDフレームワークを導入した場合、次のようなメリットがあります。
- 信頼性と一貫性のある比較可能な情報開示ができ、投資家、ステークホルダー、貸付業者に気候変動関連リスクを評価し、その財務的影響を検討する材料を提供できる
- 気候関連情報が財務情報と同様に精査されることによって、気候変動対応に関してステークホルダーからの信用や信頼が高まる
- 総合的情報に基づく効果的な資本配分ができ、低炭素社会への移行に貢献できる
- 気候関連リスクとリスクエクスポージャー評価を踏まえた短期・長期的戦略を立案できる
- 気候関連リスクの認識が深まり、金融市場全体が強化される
TCFD提言に沿った情報開示はこれまでの自主的取り組みから義務化への流れであり、正確な気候関連リスク情報開示の重要性が増しています。 規則が厳格化されるにつれ、不正確な情報開示は法的リスクになります。
>> 気候関連情報開示にTCFDが果たす役割を解説したeBook『The TCFD's Role in Emerging Climate Disclosures』をダウンロードできます
TCFD提言の実行は必須?
TCFD提言自体はあくまでも自主的な情報開示の枠組みですが、多くの国や投資家、ビジネスパートナー、その他組織の間でこれを義務付ける動きが広がっています。
TCFDフレームワークに沿った情報開示の対象者
TCFDフレームワークはどの組織も採用できます。 TCFD提言は組織の種類や法域を問わず適用できることを前提に考えられています。 また、セクター別の補助ガイダンスも用意されています。
TCFDフレームワークの基本4項目
TCFD提言では、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つの基本項目に関する開示が推奨されています。
それぞれの項目の観点から、気候関連のリスクと機会に対する企業としての対応を説明することになります。
- ガバナンス:組織のガバナンス体制とプロセスを開示する。
- 戦略:組織の戦略と財務計画に対する実際の影響、潜在的影響を開示する。
- リスク管理:リスクと機会の特定、評価、管理に用いる方法を開示する。
- 指標と目標:リスクと機会の評価と管理に用いる指標と目標を開示する。

この4つの基本項目の下に、気候関連情報開示の透明性をさらに高めるための11の推奨事項があります。 TCFD提言には従来の報告枠組みの不備を見直しながら、メインストリームの財務報告書の中で気候関連情報と財務情報を一体化させるという狙いがあります。
ガバナンス項目の開示に関する推奨事項
TCFD提言の第一層がガバナンスです。 ガバナンスの観点から気候変動の影響を評価することによって、取締役会の意思決定スピードが遅い、組織に及ぶ気候変動の影響を見える化できていないなどの全体的非効率を明らかにできます。
TCFD提言ではガバナンスに関して次のような情報開示が推奨されています。
- 気候関連のリスクと機会について取締役会による監視体制を説明する。
- 気候関連のリスクと機会の評価・管理における経営陣の役割を説明する。
戦略項目の開示に関する推奨事項
ガバナンスの次は、気候関連のリスクと機会がもたらす実際の影響と潜在的影響に着目します。 例えば、海辺にレストランを展開する飲食チェーンであれば、海面上昇や店舗営業に関わる今後の環境規制の影響を認識しておく必要があります。
TCFD提言では戦略に関して次のような情報開示が推奨されています。
- 組織にとっての短期・中期・長期的な気候関連リスクを説明する。
- 気候関連のリスクと機会が組織の戦略、事業活動、財務計画に与える影響を説明する。
- 2°C以下シナリオを含めたさまざまな気候変動シナリオを踏まえながら組織戦略のレジリエンスを説明する。
リスク管理項目の開示に関する推奨事項
リスク管理は、その企業が気候関連リスクをどのように特定し、管理しているかを明らかにするものです。 例えば、海辺にレストランを展開する飲食チェーンの経営者であれば、海面上昇を見越した新規出店場所選びの方法を考える必要があります。
TCFD提言ではリスク管理に関して次のような情報開示が推奨されています。
- 気候関連リスクの特定・評価プロセスを説明する
- 気候関連リスクの管理プロセスを説明する。
- 上記プロセスを組織全体のリスク管理計画にどのように組み込んでいるかを説明する。
指標と目標項目の開示に関する推奨事項
組織の進捗と改善を具体的に示すための指標と目標も重要な開示項目です。
例えば、海辺にレストランを展開する飲食チェーンの経営者が配管工事の欠陥による近隣ビーチへの廃水流出に気づいた場合、 目標は最終的に廃水の流出をゼロにすること、 指標はレストランからビーチへの廃水流出量になります。
もちろん、多くの組織にとって指標を決め、算出するのはこれほど単純ではありませんが、 大部分の組織には追跡すべき多くのリスクや機会があるはずです。 さらに詳しいガイダンスを知りたい方は、GHGプロトコルやPCAF(Partnership for Carbon Accounting Financials:金融向け炭素会計パートナーシップ)など、さまざまなリソースが提供されていますので参考にしてください。
TCFD提言では指標と目標に関して次のような情報開示が推奨されています。
- 自社の戦略とリスク管理プロセスに従って気候関連のリスクと機会を評価する際に用いる指標を開示する。
- スコープ1、スコープ2、さらに該当する場合はスコープ3の温室効果ガス(GHG)排出量とそれに伴うリスクを開示する。
- 気候関連のリスクと機会および指標に照らしたパフォーマンスの管理に用いる目標を説明する。
全セクター向けガイダンスと特定セクター向け補助ガイダンス
TCFDは、幅広い提言に加えて、より実務に則した手引きをまとめた全セクター向けガイダンスを公表しています。
また、補助ガイダンスではエネルギーや輸送など特定セクターの特徴が考慮されています。 気候変動の影響を最も大きく受ける金融セクターと非金融セクター向けのガイダンスもあります。 2021年に新たに公表された「Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures(気候関連財務情報開示タスクフォースの提言の実施)」は、2017年の「気候関連財務情報開示タスクフォースの提言」により詳細な解説が加えられています。
TCFDにおける気候関連のリスク、機会、財務的影響の定義
TCFDは、幅広い報告主体の開示情報を標準化するため、さまざまな気候関連のリスクと機会を分類しています。 そして自らへの影響度が大きい分類への優先的対応を推奨しています。
リスク分類
TCFDはリスクを2つに分類しています。 一つは低炭素社会への移行に伴うリスクです。 もう一つは気候変動に起因する物理的変化の結果生じるリスクです。
移行リスク
低炭素社会への移行はその過程でさまざまな物事が変化し、それらがさまざまなリスクをもたらします。 例えば、消費者がカーボンフットプリント(GHG排出量)の透明性を求めるようになれば、政策に影響する可能性があります。
移行リスクには4つの分類があります。
- 政策・法規制リスク(例:GHG排出量の多い活動に対する強制的なコストの賦課など)
- 市場リスク(例:エネルギー効率の良い製品が選好されることによる消費者需要の低下など)
- 技術リスク(例:技術進歩による従来型プロセスの陳腐化など)
- レピュテーションリスク(例:カーボンフットプリントの開示に消極的な企業に対する消費者の信頼低下など)
物理的リスク
物理的リスクでは気候変動の顕在化によって生じる変化の影響に着目します。
物理的リスクはさらに2つに分類されます。
- 慢性リスク(例:海面上昇による土地の浸食など)
- 急性リスク(例:山火事が地域の水供給に影響したことによる事業活動の停滞など)
機会
GHG排出量の削減に取り組むことによって、企業には機会も生まれます。 TCFDは期待できるいくつかの機会を示しています。
- 資源効率(例:所有建物の照明をLEDに交換するなど)
- エネルギー源(例:風力・太陽光などの低炭素エネルギー源に切り替えるなど)
- 製品・サービス(例:低炭素製品の開発など)
- 市場(例:新規市場での事業拡大など)
- レジリエンス(例:GHG排出量を抑えるための生産プロセスの効率化など)

財務的影響
TCFDは、気候関連のリスクと機会を組織の財務状態とより明確に結びつけるため、財務的影響についても分類を示しています。 主な分類は次の通りです。
損益計算書
損益計算書区分では、気候関連のリスクと機会が所定期間内の純損益に与える影響に着目します。
- 収入(例:その企業のGHG排出量の多さを理由に消費者需要が低下する場合など)
- 支出(例:その企業のサプライヤーが異常気象の影響を受けて事業を継続できない場合など)
貸借対照表
貸借対照表区分では、気候関連のリスクと機会がある時点の企業の財務的価値に与える影響に着目します。
- 資産・負債(例:山火事によって数千坪の土地が荒廃した場合など)
- 資本・資金調達(例:製品の省エネ化のために研究開発投資を必要とする場合など)
シナリオ分析とは
シナリオ分析とは、不確定要素を伴う将来のさまざまなシナリオにおいて想定される事象を検討し、評価する手法です。 シナリオ分析の目的は正確な予測や具体的な予想をはじきだすことではありません。 分析結果はあくまでも仮説であり、特定の状況が発生した場合または特定の傾向が続いた場合に起きるであろう事象を認識するためのものです。
TCFD提言では、シナリオ分析に基づき、さまざまなシナリオに照らした戦略のレジリエンスを説明することを推奨しています。 これには事業活動や財務に対して予想される影響も含まれます。
シナリオ分析は戦略に織り込んだり、あるいは投資家その他のステークホルダーに将来予想される状況に向けた組織態勢を知らせる手段にもなります。
TCFD提言では、シナリオには次の特性が必要であるとされています。
- もっともらしい(Plausible)、現実に起き得る
- 特徴的(Distinctive)であり、複数の状況の異例な重なりによって生じる結果または前例のある重なりではあるが違う結果になる場合を想定している
- 現在の傾向や動きと整合(Consistent)している(不整合を合理的に説明できる場合を除く)
- 組織の戦略または財務(あるいはその両方)に与え得る影響と関連性(Relevant)があり、その見通しを導き出すことができる
- 将来に関する一般的に認められた真実や仮定に異議を唱え(Challenging)、疑問を投げかける
報告主体がシナリオ分析を始める際に活用できるツールやリソースはいろいろあります。代表的なものは、国連食糧農業機関(FAO)が提供する気候変動に伴う農業への影響モデリングシステムであるModelling System for Agricultural Impacts of Climate Change (MOSAICC)、国際応用システム分析研究所(IIASA)が提供するシナリオエクスプローラーです。
組織に求められるシナリオ分析の種類
TCFDは好ましいシナリオと好ましくないシナリオを幅広く想定した分析を推奨しています。 2°C以下シナリオは最低限必要です。 また、報告主体と最も関連性の高いシナリオを作成することが肝要です。
作成可能なシナリオは2種類あります。
- 定性的シナリオ。シナリオ分析を開始したばかりで、同様の作業に定量情報の使用経験があまりない組織に推奨されます。
- 定量的シナリオ。複雑なデータセットの使用やモデル化に慣れている組織に最適です。

効果的なシナリオ分析を行うために
シナリオ分析の第一歩は、分析の種類、分析方法、使用する分析ツールとデータの検討です。
既存シナリオを十分理解することによって自己分析をスムーズに開始できます。 シナリオ分析の基本を理解できたら、次は想定される気候関連のリスクと機会の特定です。
リスクと機会を特定できたら、次のステップと問いに従ってシナリオ分析を当てはめます。
1. ガバナンス体制を確認する
- 組織の戦略立案やリスク管理プロセスにシナリオ分析が組み込まれていますか?
- 然るべき取締役会委員会または小委員会に監視活動が任じられていますか?
- どの内部・外部ステークホルダーがガバナンスに関与していますか?
2. 気候関連リスクのマテリアリティ評価を行う
- 気候関連のリスクと機会に対する現在および潜在的なエクスポージャーは何ですか?
- 将来的にそれらの影響度や重大性が増す可能性はありますか?
- ステークホルダーはこれらのリスクまたは機会を認識していますか?
3. シナリオ範囲を特定する
- 洗い出したエクスポージャーに対してどのようなシナリオやナラティブが適していますか?
- そのシナリオに対してどのような入力パラメーター、前提条件、分析上の選択を当てはめますか?
- 比較対象としてどのような参照シナリオを用いますか?
4. ビジネスインパクト評価を行う
- 各シナリオについて、投入コスト、営業コスト、収益、サプライチェーン、事業継続、タイミングにどのような影響がありますか?
- 主にどの事業領域の感度が高い(影響を受けやすい)と考えられますか?
5. 今後の対応を判断する
- 評価結果を踏まえ、洗い出したリスクと機会に対応するためにどのような妥当かつ現実的な判断を下しますか?
- 経営戦略や財務計画をどのように調整しますか?
6. 文書化し、開示する
- プロセスをどのように文書化しますか?
- すべての関係先に結果を知らせましたか?
- 使用した主な情報、前提条件、分析方法、結果、今後の対応を開示する準備はできましたか?

効果的な開示のための基本原則
効果的な開示のための基本原則には、質が高く有益な開示に役立つデータを使用するという共通の下地があります。
TCFDは、効果的な開示とは情報の受け手が報告主体に及ぶ可能性のある気候変動の影響を十分理解できることが大前提であると述べています。 効果的な開示の基本原則は次の通りです。
- 原則1:適切な情報を開示する
- 原則2:具体的かつ完全に開示する
- 原則3:明確に、バランスよく、分かりやすく開示する
- 原則4:時間的な一貫性を持って開示する
- 原則5:同じセクターまたはポートフォリオに属する組織と比較可能な開示を行う
- 原則6:信頼性があり、検証可能で、かつ客観的な開示を行う
- 原則7:時宜にかなった開示を行う
TCFDは1つの原則と別の原則が両立しないケースも想定しています。 例えば、開示にあたっていくつかの仮定を必要としながらも、その仮定の検証が難しい場合などです。 ここに示す基本原則は最大限従いながら、個々の折り合いを見つけることが大切です。
原則1:適切な情報を開示する
開示情報に無関係、余分、一般的な情報を含めるべきではありません。 組織の戦略を理解するに足る情報が必要です。 また、その情報が時間の経過とともに変化する場合はその点も明確に示す必要があります。
原則2:具体的かつ完全に開示する
包括的かつ過去の情報と将来を予測した情報の両方が必要です。 次の観点から情報を開示します。
- さらされる可能性のある気候変動の潜在的影響
- それらの影響の予想される性質と規模
- 気候関連リスクを管理するための組織の戦略、ガバナンス、プロセス
- 気候関連のリスクと機会の管理状況、その進捗
原則3:明確に、バランスよく、分かりやすく開示する
TCFD提言では、詳しく知りたい人に足る具体性と、理解を妨げるほど細かすぎない簡潔さが推奨されています。 また、報告主体には使用する用語の明瞭な説明と定義も求められます。
定性情報と定量情報の偏りに注意し、文章と視覚表現を織り交ぜたわかりやすい情報開示を心がけましょう。 説明では先入観を避け、リスクと機会の両方を盛り込んでください。
原則4:時間的な一貫性を持って開示する
開示の様式、指標、言葉遣いは最大限一貫性を保ち、時系列比較ができるようにします。 新たな知見や気候関連情報開示の全体的進展によって開示情報や様式を変更せざるを得ない場合もあります。 その際は変更点の説明を追記してください。
原則5:同じセクターまたはポートフォリオに属する組織と比較可能な開示を行う
開示情報には自社と他社のベンチマーク比較に足る詳細度が必要です。 財務諸表その他所定の報告書のフォーマットが統一されているのと同様に、組織間で統一された様式に従うのが望ましい方法です。
原則6:信頼性があり、検証可能で、かつ客観的な開示を行う
TCFD提言では、中立かつ正確な情報を検証可能な形で収集し、提示することが推奨されています。 これらの情報の評価においては財務情報と同等の適切な注意(デューデリジェンス)が必要です。
将来を予測した情報は組織の判断が加わりますので、信頼性や検証可能性の確保は容易ではありません。 それでも、この種の情報はできる限り客観的なデータを根拠とし、何らかの前提条件や予測を用いる場合は、その情報源を遡り、最善の評価手法を採用する必要があります。
原則7:時宜にかなった開示を行う
気候関連情報は、年次会計報告と同様、少なくとも年に1度の開示が必要です。 通常の開示タイミング以外で事業に重大な影響を与える気候関連事象が発生した場合は、遅滞なく情報開示することが推奨されます。 例えば、原油の流出や大型台風による被災などです。

ガバナンスと情報開示の主要責任者
情報開示・ガバナンスプロセスに関与すべき役職者とチームは次の通りです。
- 最高サステナビリティ責任者(CSO):環境の視点に立った気候関連のリスクと機会の特定、戦略の立案と実行、最高財務責任者(CFO)その他関係者との協力に責任を負います。
- ESGマネージャー:実行プロセスの管理、関係部署からのデータ収集を行い、気候関連情報開示とその関連報告の陣頭指揮を執ります。
- 最高財務責任者(CFO):財務の視点に立った気候関連のリスクと機会の特定、戦略の立案と実行、最高サステナビリティ責任者(CSO)その他関係者との協力に責任を負います。
- 経理責任者:関係部署からデータを収集し、気候関連データを財務報告に統合します。
- ITリード:データ収集を合理化するためのテクノロジーの活用をサポートします。
- 各チームマネージャー:チームメンバーの活動と進捗を直接監督します。
TCFD提言に沿った開示を義務付けている国や地域
現時点で対象企業にTCFD提言に沿った開示を義務付けているのは、英国、ブラジル、日本、欧州連合(EU)です。 G20およびG7加盟国もTCFDフレームワークに基づく提言の導入を公約しました。 現在、TCFDの支持は世界95の国や地域に広がっています。
カナダのように、まだTCFD提言に沿った情報開示の義務化を準備している段階か、その方向性は表明している国もいくつかあります。
TCFD賛同企業・金融機関
現在、TCFD賛同企業・金融機関は3,000を超えています。 これらの組織が、TCFD提言に沿った情報開示に取り組み、業界全体としてTCFD提言の採用を推進しています。 提言の採用は任意であり、その普及には業界のサポートが重要です。
賛同組織にはフォーラムに参加し、実務的な課題や対策を話し合う機会もあります。 賛同の表明に特に正式な条件はなく、加盟金なども必要ありません。
TCFDと他のイニシアティブや組織との関係性
TCFDの設立当初から多くのイニシアティブや組織がTCFDフレームワークを採用し、連携関係にあります。 カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト(CDP)もその一つです。TCFDを支持し、既存の開示ガイダンスや報告の仕組み、プラットフォームにTCFDフレームワークを取り入れています。 TCFDを支持する代表的組織を紹介します。
国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)
UNEP FIは、2017年に世界全体で100近い金融機関が参加したTCFDパイロットプロジェクトを開始しました。 金融業界の気候関連リスク管理をあらゆる側面から改善するための手法を見つけることが狙いです。 双方向ディスカッション、ピアプレゼンテーション、教育研修など、さまざまな機会が参加金融機関に提供されました。
これと並行して、気候関連リスクの専門家、気候モデラーなどが参加金融機関をサポートしました。 UNEP FIは、このプロジェクトの結果を踏まえて、金融業界の気候関連リスク管理と情報開示を改善するフレームワーク、ガイド、ツールを公表しています。
カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト(CDP)
2018年にCDPの開示プラットフォームはTCFDと整合したものになりました。 CDPの開示質問書はTCFDフレームワークに従って作成され、企業はTCFD提言に沿って情報を開示します。 こうした標準化によって情報比較が容易になり、CDPから情報を入手した個人や組織にとって有益な判断材料になります。
気候変動開示基準委員会(CDSB)とサステナビリティ会計基準審議会(SASB)
CDSBとSASBは、2019年にTCFD提言を導入する企業向けの「TCFD Implementation Guide(TCFD実務ガイド)」を共同発行しました。 このガイドではTCFD提言を取り入れる手段としてCDSBフレームワークとSASBスタンダードが用いられています。 TCFD提言の4つの基本項目の理解を助ける情報開示サンプルも掲載されています。